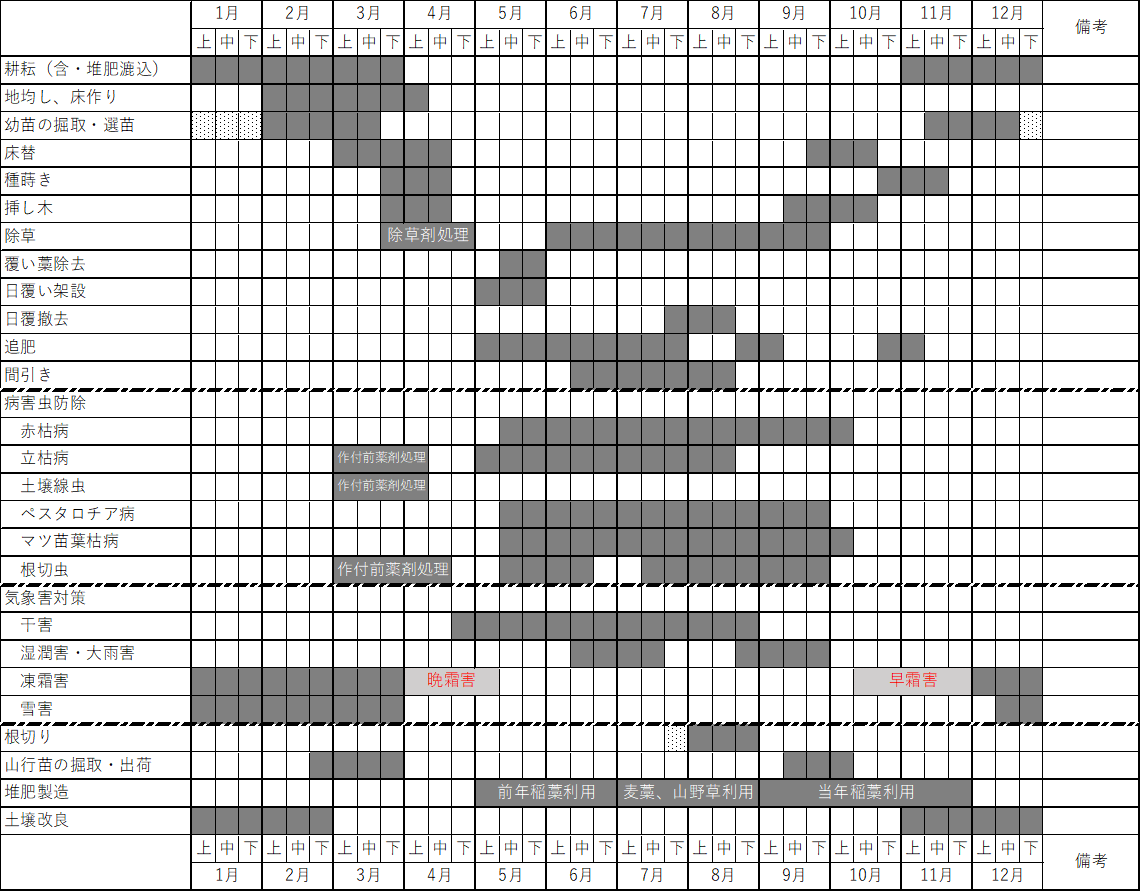| 育苗作業 |
島根県の事例(平成2年度 造林用苗木 育苗ごよみ)を基に、アレンジ中
苗畑年中行事表(島根版)
必要なこと
気象情報(月毎)
【1月】
| 作業名 |
時期・内容・要領 |
注意事項 |
| 計画の樹立 |
樹種別・苗齢別生産計画、苗畑使用計画、必要諸資材・労務等の算出、施肥設計 |
育苗標準例
施肥設計例(蒔付床・1回床替床) |
| 材料の準備・手配 |
種子、現苗、肥料、薬剤、その他材料の準備または確保のための手配をする。 |
|
| 機械器具の点検・整備 |
修理は早めに行う。 |
|
| 機材の新調・修理 |
竹簀、葦簀の編み替え、新調。
寒冷紗、ダイオネット等の補修
梱包用のコモ編み、製縄など |
|
| 雪害対策 |
越冬苗木に足しては、根雪前消毒
苗畑排水溝の設置
採種台木には支柱立て・枝条の巻締め |
雪害対策 |
| 寒害対策 |
寒害の恐れのある苗畑では、防寒施設をする。
霜柱被害の事後対策として、踏みつけ、土入れ、植え直しをする。 |
凍害・寒害対策 |
| 幼苗の掘取り・選苗 |
沿岸部など雪のないところでは実施する。
選苗は形質不良苗、規格外苗を厳選除外し、規格別に類別するほか、できるれば適宜苗長階別に仕分けする。
千秒後は、入念な土仮植をするか、適切な場所に床替時期まで貯蔵する。 |
根は長さ10cm程度に切り揃える。
土仮植は苗木を薄く並べ、根と土を密着させる。
貯蔵法(幼苗) |
| 観測地 |
平均気温
(℃) |
最高気温
平均気温 |
最低気温
平均気温 |
湿度
(%)
|
降水量
(mm) |
日照時間
(h)
|
積雪日数
(日) |
最深積雪
(cm)
|
降水日数
(日) |
| XX市 |
3.8 |
16.2
6.8 |
-6.8
0.3 |
72 |
168.5 |
76.5 |
14.3 |
89 |
20 |
| 苗畑 |
5.4 |
19.8
8.5 |
-11.5
1.2 |
76 |
112.8 |
78.2 |
8.6 |
33 |
21 |
| 霜日数 ○日 最晩積雪初日 1月▲日 |
【2月】
| 作業名 |
時期・内容・要領 |
注意事項 |
| 計画の樹立 |
1月に引き続き実施し、遅くとも今月中には完了する。 |
|
| 幼苗の掘取り・選苗 |
雪の少ない地方では1月に引き続き実施、山間部でも雪が消え次第逐次実施する。 |
1月と同じ |
| 苗畑の耕耘 |
雪の無いところでは土壌の乾き気味の時に耕耘し、同時に有機物を鋤込む。 |
耕耘時又は床作りの際に、ネキリムシ防除薬剤を鋤込む。 |
| 霜柱対策 |
霜柱のため苗木が抜けたり、根が浮いたりした苗木は被害状況に応じて、踏みつけ、土入れ、植え直しをする。 |
|
| 床替 |
下旬になり寒さが和らげれば、床替えに着手する。
着手の順序は生育の始まりの早いマツから行う。 |
床替適期基準
育成開始温度
・スギ 13~14℃
・ヒノキ 12~13℃
・アカマツ 4~5℃ |
(積雪がある場合)
雪消しと排水 |
積雪期が長引く場合、積雪下に苗木がある場所では雪消しを行う。
また、融雪時に苗畑の排水を図る。
消雪の促進には、木炭粉末、木灰、焼き籾殻、黒土等を薄く表面に散布するほか、雪面畝立て、黒色寒冷紗の雪面被覆などがある。 |
|
| 観測地 |
平均気温
(℃) |
最高気温
平均気温 |
最低気温
平均気温 |
湿度
(%)
|
降水量
(mm) |
日照時間
(h)
|
積雪日数
(日) |
最深積雪
(cm)
|
降水日数
(日) |
| XX市 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 苗畑 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 霜日数 ○日 最早積雪終日 2月▲日 |
A県の床替適期基準(一例)
| 樹種 |
山陰道 |
島嶼部 |
| 海岸部 |
中山間部 |
奥山間部 |
| スギ・ヒノキ |
3月中旬~4月上旬 |
3月下旬~4月中旬 |
4月上旬~4月中旬 |
3月下旬~4月中旬 |
| アカマツ・クロマツ |
3月上旬~3月下旬 |
3月中旬~4月上旬 |
3月下旬~4月上旬 |
3月中旬~4月上旬 |
Topへ
【3月】
| 作業名 |
時期・内容・要領 |
注意事項 |
| 幼苗の掘取り・選苗 |
遅くとも生育開始時期までに掘取りを終える。 |
晩霜害を防ぐにも早い方が良い。 |
| 床替 |
マツ→スギ→ヒノキの順で行う。
霜柱が立つ危険があるので、霜柱の酷いところでは苗間に敷き藁をして被害を防ぐ。 |
マツは芽の活動が早いので、今月中に床替えを終了する。 |
| 種の保管 |
受け取った種子は、蒔き付けまでの間、乾燥した冷暗所に保管する。
例えば。北側の納屋、地下室など |
容器は吸湿しにくく、ネズミの害を受けない物を使う。 |
| 蒔き付け床の準備 |
4月上旬には種蒔きの時期となるので、3月下旬には蒔き付け床を準備する。
予め土壌線虫と立枯病防除のための土壌消毒を行っておく。
ネキリムシ駆除のため殺虫剤を施す。 |
NCS、ドロクロール、ドジョウピクリンなどの処理をする場合は、温度と効果の関係を考慮して行う。 |
| 挿し木 |
スギ、ヒノキ等の挿し木は、下旬始めに行う。
インドール酪酸を用いた発根促進は友好。 |
品種、発根促進法 |
| 消雪の促進 |
雪が残ってる場合は、消雪を促進する。 |
融雪時の排水に留意する。 |
| 山行苗の掘取り・出荷 |
春出し山行苗の掘取り・選苗・荷造りは、苗木の需要に応じて速やかに行う。 |
|
| 観測地 |
平均気温
(℃) |
最高気温
平均気温 |
最低気温
平均気温 |
湿度
(%)
|
降水量
(mm) |
日照時間
(h)
|
積雪日数
(日) |
最深積雪
(cm)
|
降水日数
(日) |
| XX市 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 苗畑 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
霜日数 ○日
降雪終日 平均3月●日 最早 3月□日 最晩 4月■日
積雪終日 平均3月▲日 最早 2月★日 最晩 3月◆日 |
【4月】
| 作業名 |
時期・内容・要領 |
注意事項 |
| 床替 |
スギ、ヒノキの床替時期にあたるが、山間部であっても4月中旬には完了することが望ましい。 |
この時期は乾燥しやすいので苗木はコモ包みにするが、手桶を入れて持ち運びする。 |
| 種蒔き |
上~中旬が種蒔き時期、なるべく早く蒔くと同時に発芽促進処理をして、発芽率と発芽勢を強める。
種に消毒して立枯病を予防する。
適量蒔き付けに留意する。 |
発芽促進処理法
種の消毒法
蒔き付け量計算例
種の発芽温度(℃)
| 樹種 |
最低温度 |
最適温度 |
最高温度 |
| スギ |
8~9 |
20 |
29~30 |
| ヒノキ |
8~9 |
26~30 |
35~36 |
| アカマツ |
9 |
21~25 |
35~36 |
| クロマツ |
春蒔きの適期基準
| 場所 |
開始 |
終わり |
| 山陰道 |
海岸部 |
3月下旬 |
4月上旬 |
| 中山間部 |
4月上旬 |
4月中旬 |
| 奥山間部 |
4月後半 |
4月中旬 |
| 島嶼部 |
4月上旬 |
4月中旬 |
|
| 挿し木 |
スギ、ヒノキの挿し木も中旬のうちには終わらせる。
スギの採穂適期は芽の活動直前又はソメイヨシノの開花期の半旬前とされているので時期を失しないようにする。 |
|
| 除草剤施用 |
1回目施用時期は、床替床では床替え直後またはしばらくして地表面が安定してから、蒔き付け床では覆土直後である。 |
標準施用法 |
| 灌水 |
床替や挿し木直後、蒔き付け床の乾燥は、活着も発根、発芽などに大きな影響を及ぼす。状況に応じて随時灌水する。 |
|
| 晩霜対策 |
今月中~下旬から5月初めの晩霜は発芽初期の蒔き付け苗や新梢の伸び始めた床替苗に被害を与えるので蒔き付け苗では、タスケ、クレモナ寒冷紗、ダイオネット等の日除覆を早く取り付けて霜除けとする。
床替床でも、被覆法、燻煙法、散水法等可能な防霜対策を講ずる。 |
ラジオ、テレビ、有線放送などの霜注意報に留意する。 |
| 観測地 |
平均気温
(℃) |
最高気温
平均気温 |
最低気温
平均気温 |
湿度
(%)
|
降水量
(mm) |
日照時間
(h)
|
積雪日数
(日) |
最深積雪
(cm)
|
霜日数
(日) |
降水日数
(日) |
| XX市 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 苗畑 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最晩降雪終日 ▲月◆日
ソメイヨシノ開花日 平均◎月○日 最早 ■月◆日 最晩 ★月▼日
晩霜終日 平均●月★日 最早 ☆月□日 最晩 ▲月■日 |
Topへ
【5月】
| 作業名 |
時期・内容・要領 |
注意事項 |
| 覆い藁の除去 |
適期に蒔かれたものは5月初めから中頃にかけて発芽が完了するが、覆い藁は子苗が半分程度に生えた頃から生えそろうまでの間に2~3回に分けて徐々に取り除く。
ただし、乾燥が続いたり、今後乾燥が予想さる場合は、覆い藁の半分くらいを梅雨頃まで残しておく。 |
床替え、さし木あるいは発芽後間もない時期で、苗木は外界の影響を最も受けやすいので管理には十分注意する。 |
| 日覆いの取り付け |
日覆いは覆い藁を全部取り除いた時点ではかけておかねばならないので、前もって取り付けの準備をしておき、覆い藁の最終除去と同時またはそれ以前に取り付ける。
日覆いの高さは一般に40~50cmとする。 |
日覆いは夜間、曇雨天時には取りはずす。 |
| 薬剤散布 |
スギの赤枯病、マツ苗の葉枯病予防のためのボルドー液、マンネブ剤等による消毒は今月中旬から開始し、今後定期散布する。 |
薬剤散布法
薬剤防御法 |
| 除草 |
雑草は小さいうちに抜き取る。
蒔き付けまたは床替え直後に除草剤を処理した場合でも、今月中~下旬には2回目の処理が必要となる。 |
蒔き付け床では発芽間もない幼弱なときには処理をひかえ、初生葉が開ききってある程度硬くなってから処理する。 |
| 追肥 |
施肥設計または苗木の生育状況に応じて適宜追肥する。 |
|
| 観測地 |
平均気温
(℃) |
最高気温
平均気温 |
最低気温
平均気温 |
湿度
(%)
|
降水量
(mm) |
日照時間
(h)
|
霜日数
(日) |
日照率
(%) |
降水日数
(日) |
| XX市 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 苗畑 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
晩霜終日 平均●月★日
梅雨入り最早日 ■月◆日 |
【6月】
| 作業名 |
時期・内容・要領 |
注意事項 |
| 間引き |
1回目の間引きを梅雨入り後から中旬にかけて行う。発芽が遅かったところでは混み具合に応じて若干遅らせてもよい。 |
間引きの要領
スギの目安
苗長3cm
過密部分の調整、発育不良苗、被害苗、形質不良苗
苗床の空気の流通を図る。 |
| 除草 |
梅雨期は雑草が繁茂し、環境が.悪化しやすい為、梅雨入りまでに、雑草を抜きとり、除草剤で処理する。 |
| 日覆いの一時除去 |
蒔き付け床、挿し木床の日覆いは曇雨天のときはっとめて除去する。 |
|
| 薬剤散布 |
梅雨期は高温多湿となりがちで、赤枯病、マツの葉枯病、稚苗の立枯病、くもの巣病など病害が発生し易いので適切な防除散布につとめる。 |
赤枯病、葉枯病に対する薬剤の定期散布間隔は、平常より5日くらい短縮し、雨の合間に入念に行う。
その他
病害虫薬剤駆除法※ |
| 水害対策 |
事前対策
水田転換地、低地等では、堤防・畦詳の補強、排水溝の設置又は浚せつ。
事故対策
浸入・停滞水の速やかな排除。
苗床表土の流失被害には土入れによる根株の固定又は植替え。
流入土砂の除去、病害予防のための消毒、衰弱苗木の樹勢回復のための施肥。 |
土壌条件等によっては、葉面施肥が有効。 |
| 水蝕害対策 |
傾斜地苗畑では地表に稲ワラ、麦ワラ、山草等を敷く。
敷ワラは土壌が乾燥しないときに中耕後傾斜面に対し、直角に敷くのが効果的である。浸蝕を受け根株が露出した苗、倒伏苗に対しては土入れをして株起こしする。 |
|
| 湿潤害対策 |
梅雨期はとかく過湿になり易いので常に排水をよくし、時には中耕をして土壌の通気性を高める。 |
|
| 観測地 |
平均気温
(℃) |
最高気温
平均気温 |
最低気温
平均気温 |
湿度
(%)
|
降水量
(mm) |
日照時間
(h)
|
日照率
(%) |
降水日数
(日) |
| XX市 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 苗畑 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 梅雨入り平均 ■月◆日 最早 ●月★日 最晩 ▲月▼日 |
Topへ
【7月】
| 作業名 |
時期・内容・要領 |
注意事項 |
| 間引き |
2回目の間引きは今月の上~中旬に土壌が湿っているときに実施する。
間引きの割合は間引き予定量の三割程度とするが、初めての場合は6割くらいとする。 |
スギの目安
枝2~3本
過密部分の調整、発育不良苗、被害苗、形質不良苗
※苗木の根がかなり貼った場合は、間引きせず、摘み取ること。 |
| 追肥 |
施肥設計あるいは苗木の生長・色微等に応じて適当な養分を適量追肥する。
成長の促進を目的とした窒素分の追肥は7月中に施しておく。
要素欠乏症も目に付く頃となる。特に、リン酸欠乏に対しては、速やかに葉面施肥をするほか、液肥等速効肥料の土壌施肥を行う。 |
追肥は雨後除草して行う。
要素欠乏症の検索表
要素欠乏症と対策 |
| 除草 |
雨期の後期から梅雨明け直後にかけて入念な除草を行うと共に、除草剤を散布する。 |
間伐期に向かうが、除草を繁茂させないことが、干害の間接防除となる。 |
| 薬剤散布 |
梅雨期は高温多湿となりがちで、赤枯病、マツの葉枯病、稚苗の立枯病、くもの巣病など病害が発生し易いので適切な防除散布につとめる。 |
赤枯病、葉枯病に対する薬剤の定期散布間隔は、平常より5日くらい短縮し、雨の合間に入念に行う。
その他病害虫薬剤駆除法※ |
| 水害対策 |
事前対策
水田転換地、低地等では、堤防・畦畔の補強、排水溝の設置又は浚渫。
事故対策
浸入・停滞水の速やかな排除。
苗床表土の流失被害には土入れによる根株の固定又は植替え。
流入土砂の除去、病害予防のための消毒、衰弱苗木の樹勢回復のための施肥。 |
土壌条件等によっては、葉面施肥が有効。 |
水蝕害対策
※6月と一緒 |
傾斜地苗畑では地表に稲ワラ、麦ワラ、山草等を敷く。
敷ワラは土壌が乾燥しないときに中耕後傾斜面に対し、直角に敷くのが効果的である。浸蝕を受け根株が露出した苗、倒伏苗に対しては土入れをして株起こしする。 |
|
湿潤害対策
※6月と一緒 |
梅雨期はとかく過湿になり易いので常に排水をよくし、時には中耕をして土壌の通気性を高める。 |
|
| 堆肥製造 |
麦わら、山野草または前年の稲藁を原料に堆肥の積込 |
堆肥製造法 |
| 観測地 |
平均気温
(℃) |
最高気温
平均気温 |
最低気温
平均気温 |
湿度
(%)
|
降水量
(mm) |
日照時間
(h)
|
日照率
(%) |
降水日数
(日) |
| XX市 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 苗畑 |
|
|
|
|
|
|
|
|
梅雨明け平均 ■月◆日 最早 ●月★日 最晩 ▲月▼日
過去の豪雨降水量 ●●年豪雨記録 ■■市 XXXmm
過去の干魃降水量と無降水日数 ▲▼町 XXmm ●☆日 |
【8月】
| 作業名 |
時期・内容・要領 |
注意事項 |
| 間引き |
今月の上~中旬が最終回の間引き時期である。
理想としては雨後土壌が湿っている時がよいが、日照り続きで土壌が乾燥しているときは苗木は抜き取らずに、地際から切り取る。 |
|
| 除草 |
状況に応じ手取除草又は除草剤の施用 |
|
| 薬剤散布 |
赤枯病、葉枯病予防薬剤の定期散布のほか突発病害虫の防除のための薬剤散布 |
|
| 干害対策 |
気温が最も高い月で日照りが続けば干害が起こる可能性が高いので対策を怠たらないように。
①平素から除草を徹底し雑草による土壌水分の蒸散を防ぐ
②敷ワラ、籾ガラ、鋸屑による地表被覆
③風除け、日除けの取付け
④中耕
⑤千害が切迫したら水 |
灌水量の一例
| 土壌の種類 |
土層10cmに対する1回の灌水量 |
| 壌土 |
15~20ミリ
(15~20㍑/m2) |
| 砂質土 |
6~10ミリ
(6~10㍑/m2) |
土層20cmの場合は倍量
灌水の有効日数-夏期干天時-
潅水は早朝又は夕刻に行い、降雨があるまで継続する。 |
| 台風対策 |
中、下旬後台風期となる。台風情報に応じ、①日覆その他台風に飛ばされやすい野外施設の取込み又は補強②高温多湿によって発生とまん延が助長される病害(赤枯病、葉枯病、立枯病、根腐病、くもの巣病、ペスタロチア病)防除のための入念な消毒、環境改善 |
スギ、ヒノキは台風によって枝葉が触れ合ったりして傷つくと、ペスタロチア病が発生しやすいので、とくに台風の前後に消毒する |
| 根切り |
その年の気象条件や場所によっては8月のうちにも根切りが必要になるが、中〜下旬以後適度の降雨があり、実施条件(9月掲載)が満たされれば根切りを行う |
|
| 堆肥製造 |
稲ワラ(前年産)、麦ワラ、山野草等を原料とした積込み |
堆肥製造法 |
| 観測地 |
平均気温
(℃) |
最高気温
平均気温 |
最低気温
平均気温 |
湿度
(%)
|
降水量
(mm) |
日照時間
(h)
|
日照率
(%) |
降水日数
(日) |
| XX市 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 苗畑 |
|
|
|
|
|
|
|
|
最晩梅雨明け ▲月▼日
過去の豪雨降水量 ●●年豪雨記録 ■■市 XXXmm
過去の干魃降水量と無降水日数 ▲▼町 XXmm ●☆日 |
Topへ
【9月】
| 作業名 |
時期・内容・要領 |
注意事項 |
| 根切り |
今月に入るとスギ、ヒノキ苗の本格的な秋伸びが盛んになるので根切りを行う。
実施時期は苗木の長さが規格に達していることと霜の降りる1~1.5月を目安として決めるが、●▲県の平年では9月上旬から下旬前半の間である。
根切りを行う日は陽ざしが弱いか曇天で無風の日を選び、しかも土壌に適当な湿りがあるときに行う。
根切りの深さは、まきつけ苗で7cm、床替苗で12~15cn程度とする |
根切り時期が遅いと細根の発達促進と早霜害防止の効果が少なくなる。
晴天が続き土壌が乾ききっているとき、陽射しや風が強いときは避ける。
根切り作業功程
| 人力用根切すき |
蒔き付け床1人1日4a
1回床替1人1日8,000本 |
| 高営式根切機 |
床面10a
蒔き付け床70~80分
床替床50~60分 |
| 高森式根切機 |
1日30~50a
(人力では10a当り3人) |
|
| 秋挿し木 |
9月中旬から10月中旬が秋さしの適期である。さし穂のかたまり具合と天候条件をにらみ合せて実施する |
残暑がやわらぎ適度な降雨があってからが良い。 |
| 日覆の撤収 |
まきつけ床やさしき床の日覆は上旬には除去する。もし陽ざしが強ければ朝や夕方に一時的に除き苗木を馴らしながら数日をかけて徐々に取り除く |
|
薬剤散布
※8月と一緒 |
赤枯病、葉枯病予防薬剤の定期散布のほか突発病害虫の防除のための薬剤散布 |
|
台風対策
※8月と一緒 |
中、下旬後台風期となる。台風情報に応じ、①日覆その他台風に飛ばされやすい野外施設の取込み又は補強②高温多湿によって発生とまん延が助長される病害(赤枯病、葉枯病、立枯病、根腐病、くもの巣病、ペスタロチア病)防除のための入念な消毒、環境改善 |
スギ、ヒノキは台風によって枝葉が触れ合ったりして傷つくと、ペスタロチア病が発生しゃすいので、とくに台風の前後に消毒する |
| 除草 |
この頃の雑草は著しい繁茂でない限り苗木の生長を抑制することは少ないが環境を悪化するし、また結実期のものが多いので種実の落下しないうちに除草する |
|
| 追肥 |
加里を初秋のうちに追肥する。また、石灰を施して徒長を防ぎ、根系の発達をはかる |
|
| 堆肥製造 |
早期栽培稲藁を材料として作る。 |
堆肥製造法 |
| 観測地 |
平均気温
(℃) |
最高気温
平均気温 |
最低気温
平均気温 |
湿度
(%)
|
降水量
(mm) |
日照時間
(h)
|
日照率
(%) |
降水日数
(日) |
| XX市 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 苗畑 |
|
|
|
|
|
|
|
|
【10月】
| 作業名 |
時期・内容・要領 |
注意事項 |
| 薬剤散布 |
赤枯病、葉枯病防除のための薬剤は今月の上〜中旬にかけて最後の散布をする。 |
感染期は今月の中旬まである。 |
| 追肥 |
弁当肥は地上生長のほほ停止した今月下旬から11月上旬に追肥する。 |
来春の床替後、または造林後の成長が促進される。 |
| 秋挿し木 |
今月の中旬までが適期であるのでなるべく早目にさしつける |
苗間に藁、籾殻、落葉等を被覆して、乾燥防止、保温、霜柱防止のように役立てる。 |
| 秋床替 |
上・中旬が適期である。
霜柱が強くないところでは実施する |
| 山行き苗の掘取り |
今月下旬頃から開始。
掘取りは風の強いときをさけ、つとめて曇天無風の日や朝夕の陽ざしの弱いときに行う。
掘った苗木は直ちにコモ、ムシロなどで覆う。 |
根を極端に短く切らぬこと
枝葉に傷をつけないこと。
苗木を乾燥させないこと
|
| 選苗 |
日陰または屋内で行う。規格別に選別するが、形質不良苗、被害苗、結実着花苗は厳選除外する |
陽光や風が当るところでは選苗、荷造りをしないこと
苗木規格 |
| 剪根 |
根の長過ぎるものは20cm程度に切りつめる |
鋭利な刃物を用いて切る |
| 荷造り |
根の乾燥防止処理として、
①泥づけ、
②根の間に湿ったオガクズを入れる
③半腐れワラ、水ゴケで根を包む
のいずれかを行う。
また、ヒノキ、マツは枝業のムレを防ぐため梱包の中心に直径10cm内外のソダを入れる。 |
泥づけ法
畑地に直径1〜2m、深さ1m内外の穴を掘る。
これに表土と下層の粘土を少量と水を加えてドロドロの泥水を作り、苗木の根部を束のまま泥水につける。 |
| 堆肥製造 |
稲藁のできる時期なので早目に積込む。 |
堆肥製造法 |
| 種の採取調製 |
10月に入るとタネは成熟する。球果の熟れ具合(色調)を観察し、それぞれ適期に採取する。 |
種苗法では、9月20日以降
| 樹種 |
時期 |
| スギ |
10月中旬~下旬 |
| ヒノキ |
10月上旬~11月中旬 |
アカマツ
クロマツ |
10月中旬~下旬 |
|
| 観測地 |
平均気温
(℃) |
最高気温
平均気温 |
最低気温
平均気温 |
湿度
(%)
|
降水量
(mm) |
日照時間
(h)
|
日照率
(%) |
降水日数
(日) |
| XX市 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 苗畑 |
|
|
|
|
|
|
|
|
初霜 最早 ●月▲日
初霜最早日 XX市 ●月▼日 XX村 ●月■日 |
種子の採取~貯蔵及び標準諸量
| 樹種 |
開花期 |
種子の
成熟期 |
採取調整法 |
貯蔵法 |
重量(g) |
粒数(千粒) |
| 千粒 |
1㍑ |
1㍑ |
1kg |
| スギ |
3~4月 |
10月 |
球果採集→乾燥→脱粒
→風選→石鹸液選(水選) |
乾燥、低温貯蔵
硫化加里有効 |
3.1 |
370 |
121 |
326 |
| ヒノキ |
2.2 |
290 |
132 |
449 |
| アカマツ |
4~5月 |
開花翌年
10月 |
球果採集→乾燥→脱粒
→翅除去→風選
脱粒困難な場合は、浸水温湯処理 |
乾燥、低温貯蔵 |
9.0 |
540 |
57 |
107 |
| クロマツ |
13.0 |
520 |
39 |
74 |
Topへ
【11月】
| 作業名 |
時期・内容・要領 |
注意事項 |
| 山行苗の掘取り・出荷 |
なるべく早い時期に完了する。 |
参考資料:山行苗輸送標準積載量(6トン積トラック) |
| 越冬仮植 |
| 時期 |
年内に十分活着することが必要なので、なるべく早い時期に行う。 |
| 場所 |
東から南向きの斜面などで雪解けが早くて風当たりの穏やかな排水の良いところ、土壌は通気性と透水性の良いものを選び、排水溝を設ける。 |
| 方法 |
|
|
仮植すると苗木は一時的に衰弱し、それが回復しないうちに低温や根雪になると抵抗性が弱く被害を受けやすくなる。
被害を受ける前に、十分活着させることが大切。
水が停滞すると根腐れを起こし、また過湿になりやすく融雪期に、雪腐病発生、蔓延の原因となる。 |
| 耕耘 |
苗を掘り取って空いた畑はなるべく秋のうちに耕耘する。土壌改良のため実態に応じた耕耘法を実行する。
深耕は隔年で実施する。
秋耕時に生藁を鋤込み、春までに土中で堆肥化させる。 |
秋耕は冬期間に土壌の風化や潜在養分の分解を促進したり、害虫を投資させるなどの効果がある。
固結した重粘土壌では特に必要である。
耕耘時の生藁鋤込み法 |
| 土地改良 |
客土、排水溝の設置等土壌改善に必要な作業を休閑中に実施しておく。 |
苗木と土壌酸性度
石灰施用による酸性土壌の矯正
苗畑の土壌管理 |
| 観測地 |
平均気温
(℃) |
最高気温
平均気温 |
最低気温
平均気温 |
湿度
(%)
|
降水量
(mm) |
日照時間
(h)
|
日照率
(%) |
降水日数
(日) |
霜日数 |
| XX市 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 苗畑 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初霜日 平均 ●月▲日 最早 ●月▼日 最晩 ●月■日
初雪日 最早 ●月▼日 積雪初日 最早 ●月■日 |
|
【12月】
| 作業名 |
時期・内容・要領 |
注意事項 |
| 耕耘 |
苗を掘り取って空いた畑はなるべく秋のうちに耕耘する。土壌改良のため実態に応じた耕耘法を実行する。
深耕は隔年で実施する。
秋耕時に生藁を鋤込み、春までに土中で堆肥化させる。 |
秋耕は冬期間に土壌の風化や潜在養分の分解を促進したり、害虫を投資させるなどの効果がある。
固結した重粘土壌では特に必要である。 |
| 土地改良 |
客土、排水溝の設置等土壌改善に必要な作業を休閑中に実施しておく。 |
|
| 雪腐病予防消毒 |
越冬苗木に対して、根雪になる前に薬剤消毒をして雪腐れ病の予防を図る。
薬剤と処理法
①4-4式ボルドー液、チウラム剤、キャプタン剤の400~500倍液を地面が潤う程度に散布する。
②チウラム剤、PCNB剤の水和液を粉態のまま5g/m2、キャプラン剤を粉態のまま5~10g/m2散布する。 |
・アカマツ苗はボルダー液では薬害を受けるので使用しない。
・散布後根雪になるのが遅れた場合は、もう一度散布する。
・仮植苗は被病し易いので特に念入りに消毒する。 |
| 防寒・防霜 |
秋床替やスギの秋挿しをした苗畑で℃所が凍結したり、霜柱が立つ恐れがあるところでは、風よけ、霜よけを設けるか、苗間に稲藁、籾殻、鋸屑などを敷く。 |
凍害・寒害対策 |
| 土壌の調査診断 |
土壌の断面積、科学性の簡易検定等を行い、次年度の土壌管理、肥培管理を的確なものとする。 |
|
| 観測地 |
平均気温
(℃) |
最高気温
平均気温 |
最低気温
平均気温 |
湿度
(%)
|
降水量
(mm) |
日照時間
(h)
|
積雪日数
(日) |
最深積雪
(cm)
|
降水日数
(日) |
| XX市 |
3.8 |
16.2
6.8 |
-6.8
0.3 |
72 |
168.5 |
76.5 |
14.3 |
89 |
20 |
| 苗畑 |
5.4 |
19.8
8.5 |
-11.5
1.2 |
76 |
112.8 |
78.2 |
8.6 |
33 |
21 |
霜日数 ○日 初霜 最晩 ★月▲日
初雪日 平均 ●月■日 最早 ◆月▼日 最晩 ●月■日
積雪初日 平均●月▼日 最早★月▲日 最晩 ▲月▼日 |
Topへ |
メモ
山行苗1万本養成に必要な種子、苗畑面積(大阪営林局情報)
| 樹種 |
種子量
g |
発芽効率
% |
播種床(m2) |
要床替
得苗数 |
床替床(m2) |
1回床替
山行苗 |
| 床地 |
附属地 |
計 |
床地 |
附属地 |
計 |
| スギ |
764 |
25 |
25 |
13 |
38 |
12,500 |
256 |
86 |
342 |
10,000 |
| ヒノキ |
1,266 |
20 |
23 |
12 |
35 |
12,500 |
224 |
75 |
299 |
10,000 |
| アカマツ |
453 |
90 |
29 |
15 |
44 |
12,000 |
245 |
82 |
327 |
10,000 |
| クロマツ |
660 |
90 |
29 |
15 |
44 |
12,000 |
245 |
82 |
327 |
10,000 |
| 仕立て基準 |
スギ |
ヒノキ |
マツ |
| 播種床1m2当り得苗本数 |
500 |
550 |
450 |
| 床替床1m2当り床替本数 |
49 |
56 |
49 |
※地域によって数字が増減する。
|
実生苗の育苗標準例
| 樹種 |
区分 |
仕立本数
(本/m2) |
得苗率 |
山行苗10万本当り |
1ha当り
山行苗
生産本数
(千本) |
摘要 |
本数
(千本) |
面積 |
| 床地 |
附属地 |
計 |
| スギ |
蒔き付け |
600 |
100 |
121.3 |
202 |
101 |
303 |
|
検定発芽率30%
m2当り蒔き付け量30g
10万本生産に必要な種子量6.06kg
2年生山行苗、2回床替苗の得苗率は1回目の床替苗の得苗本数に対するもの |
| 1回床替 |
49 |
|
121.3 |
2476 |
743 |
3,219 |
|
| 得苗 |
|
85 |
10.1 |
|
|
|
|
| 2年生山行苗 |
|
80 |
82.5 |
|
|
|
|
| 2回床替 |
36 |
30 |
20.6 |
572 |
172 |
744 |
234.4 |
| 3年生山行苗 |
|
85 |
17.5 |
|
|
|
|
| 計 |
|
|
100.0 |
3,250 |
1,016 |
4,266 |
(252.3) |
| ヒノキ |
蒔き付け |
800 |
100 |
145.3 |
182 |
91 |
273 |
|
検定発芽率200%
m2当り蒔き付け量33g
10万本生産に必要な種子量6.01kg
2年生山行苗、2回床替苗の得苗率は1回目の床替苗の得苗本数に対するもの |
| 1回床替 |
64 |
|
145.3 |
2,271 |
681 |
2,952 |
|
| 得苗 |
|
80 |
116.2 |
|
|
|
|
| 2年生山行苗 |
|
30 |
34.9 |
|
|
|
|
| 2回床替 |
42 |
70 |
81.3 |
1,936 |
581 |
2,517 |
174.2 |
| 3年生山行苗 |
|
80 |
65.1 |
|
|
|
|
| 計 |
|
|
100.0 |
4,389 |
1,353 |
5,742 |
(182.8) |
| アカマツ |
蒔き付け |
500 |
100 |
125.0 |
250 |
125 |
375 |
|
検定発芽率70%
m2当り蒔き付け量20g
10万本生産に必要な種子量5.0kg |
| 1回床替 |
49 |
|
125.0 |
2,551 |
765 |
3,316 |
270.9 |
| 2年生山行苗 |
|
80 |
100.0 |
|
|
|
|
| 計 |
|
|
100.0 |
2,801 |
890 |
3,691 |
(301.6) |
| クロマツ |
蒔き付け |
500 |
100 |
125.0 |
250 |
125 |
375 |
|
検定発芽率80%
m2当り蒔き付け量16.7g
10万本生産に必要な種子量4.18kg |
| 1回床替 |
49 |
|
125.0 |
2,551 |
765 |
3,316 |
270.9 |
| 2年生山行苗 |
|
80 |
100.0 |
|
|
|
|
| 計 |
|
|
100.0 |
2,801 |
890 |
3,691 |
(301.6) |
※計の(111.1)は床替のみの場合
Topへ
|
施肥設計例
①蒔き付け床(1m2当りg)
| 施肥 |
スギ・埴質壌土 |
アカマツ・砂質壌土 |
| 区分 |
肥料 |
施肥量 |
施肥要素量 |
施肥量 |
施肥要素量 |
| 肥料名 |
含水率 |
N |
P |
K |
N |
P |
K |
| 基肥 |
堆肥 |
70
0.6-0.2-0.4 |
1,875 |
3.4 |
1.1 |
2.2 |
1,875 |
3.4 |
1.1 |
2.2 |
| 鶏糞 |
3-3-1.2 |
|
|
|
|
50 |
1.5 |
1.5 |
0.6 |
| 硫安 |
21 |
33 |
6.9 |
|
|
20 |
4.2 |
|
|
| 過石 |
17 |
30 |
|
5.1 |
|
20 |
|
3.4 |
|
| 熔燐 |
19 |
20 |
|
3.8 |
|
12 |
|
2.3 |
|
| 塩加 |
60 |
4 |
|
|
2.4 |
2 |
|
|
1.2 |
| 小計 |
|
10.3 |
10.0 |
4.6 |
|
9.1 |
8.3 |
4.0 |
| 追肥 |
尿素 |
46 |
10 |
4.6 |
|
|
13 |
6.0 |
|
|
| 硫化 |
50 |
4 |
|
|
2.0 |
2 |
|
|
1.0 |
| 小計 |
|
4.6 |
|
2.0 |
|
6.0 |
|
1.0 |
| 合計 |
|
14.9 |
10.0 |
6.6 |
|
15.1 |
8.3 |
5.0 |
②1回床替床(1m2当りg)
| 施肥 |
スギ・埴質壌土 |
アカマツ・砂質壌土 |
| 区分 |
肥料 |
施肥量 |
施肥要素量 |
施肥量 |
施肥要素量 |
| 肥料名 |
含水率 |
N |
P |
K |
N |
P |
K |
| 基肥 |
堆肥 |
70
0.6-0.2-0.4 |
1,875 |
3.4 |
1.1 |
2.2 |
1,875 |
3.4 |
1.1 |
2.2 |
| 鶏糞 |
3-3-1.2 |
|
|
|
|
100 |
3.0 |
3.0 |
1.2 |
| 硫安 |
21 |
50 |
10.5 |
|
|
40 |
8.4 |
|
|
| 過石 |
17 |
30 |
|
5.1 |
|
20 |
|
3.4 |
|
| 熔燐 |
19 |
35 |
|
6.8 |
|
25 |
|
4.7 |
|
| 塩加 |
60 |
7 |
|
|
4.2 |
3 |
|
|
1.8 |
| 小計 |
|
13.9 |
13.0 |
6.4 |
|
14.8 |
12.2 |
5.2 |
| 追肥 |
硫安 |
21 |
|
|
|
|
10 |
2.1 |
|
|
| 尿素 |
46 |
20 |
9.2 |
|
|
12 |
5.5 |
|
|
| 硫化 |
50 |
6 |
|
|
3.0 |
3 |
|
|
1.5 |
| 小計 |
|
9.2 |
|
3.0 |
|
7.6 |
|
1.5 |
| 合計 |
|
23.1 |
13.0 |
9.4 |
|
22.4 |
12.2 |
6.7 |
施肥要素量計算例-1回床替2年生の場合1m2当り-
| 樹種 |
育苗目標 |
乾物重
g |
苗木の養分
組成対乾物% |
苗木の養分
吸収量(B)g |
養分天然
供給量(C)g |
施肥要素量
(A)g |
| 生体重 |
床替本数 |
N |
P |
K |
N |
P |
K |
N |
P |
K |
N |
P |
K |
| スギ |
80g |
49 |
1,176 |
1.3 |
0.23 |
1.0 |
15.3 |
2.7 |
11.8 |
6.1 |
1.4 |
7.1 |
23.0 |
13.0 |
9.4 |
| ヒノキ |
50g |
56 |
840 |
1.3 |
0.24 |
1.0 |
10.9 |
2.0 |
8.4 |
4.4 |
1.0 |
5.0 |
16.3 |
10.2 |
6.8 |
| アカマツ |
60g |
56 |
1,008 |
1.8 |
0.30 |
0.8 |
18.1 |
3.0 |
8.1 |
9.1 |
1.8 |
5.6 |
22.5 |
12.0 |
5.0 |
| クロマツ |
70g |
56 |
1,176 |
1.8 |
0.30 |
0.8 |
9.4 |
3.5 |
9.4 |
10.6 |
2.1 |
6.6 |
26.5 |
14.0 |
5.6 |
①計算は、
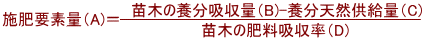
の還元法による。
②苗木の含水率は70%として計算。
➂(C)の値は(B)の値に対し、スギ、ヒノキではN:40%,P:50%、K:60%、マツではN:50%,P:60%,K:70%を乗して求めた。
④(D)は各樹種ともN:40%,P:10%,K:50%とした。
|
貯蔵法(幼苗)
| 1.貯蔵条件 |
|
苗木を休眠状態に保ちながら、乾燥による萎凋と気温・多湿による腐敗を防ぐため、温度は、1~5℃、関係湿度は85~90%ととし、適度の換気を図る。 |
| 2.貯蔵施設 |
|
地下室、半地下式土囲い室、横穴式貯蔵庫等 |
| 3.苗木保管法 |
① |
苗木を棚積みして根と値を合わせ、それを水苔などで軽く覆っておく。 |
|
② |
床が土間の場合は、束のまま根を土に密着させ、束と束の間は絶対に隙間が出来ないように並べる。 |
|
③ |
CTM段ボール箱内に収納するか、ライフパック等の保湿性梱包資材で梱包し、貯蔵施設内で保管する。 |
|
|
|
床替の標準間隔
| 樹種 |
植え付け法 |
m2当り床替本数 |
植え付け間隔 |
| 1回床替 |
2回床替 |
床植え |
2条列植え(並木植え) |
| スギ |
床植え |
42~49 |
36~42 |
m2当り
本数 |
間隔
株×株cm |
| 36 |
18×18 |
| 42 |
15×18 |
| 49 |
15×15 |
|
m2当り
本数 |
間隔
株×株cm |
| 24 |
16.6×15×35 |
| 28 |
14.3×15×35 |
| 32 |
12.5×15×35 |
| 36 |
11.1×15×35 |
|
| 2条列植え |
28~32 |
24~28 |
| ヒノキ |
床植え |
42~49 |
36~42 |
| 床植え(3年生) |
56~64 |
|
| 2条列植え |
32~36 |
28~32 |
アカマツ
クロマツ |
床植え |
49 |
|
| 2条列植え |
28~36 |
|
Topへ
|
薬剤防御法
土壌消毒による土壌線虫・立枯病等の防除法(蒔き付け前)
| 薬剤 |
濃度・施用量 |
処理法 |
注意点 |
カーバム剤
NCS |
2倍液
50cc/m2 |
| 注入点 |
30cm間隔の千鳥状に1m2当り10穴、注入の深さは15cm程度 |
| 注入量 |
1穴あたり5cc、注入後穴を踏み固めて塞ぐ |
注入後直ちにポリエチレンフィルムなどで被覆。
7~10日経過後、除覆
ガス抜き(表土10cmくらいの範囲を打ち返す)
約1週間後に蒔き付ける。 |
・クロルピクリン剤は劇薬のため、ゴム製手袋、メガネ、防毒マスクなどを着用する。
・覆土用土も同一薬剤で消毒しておく。
・地温11℃以上であれば使用できる。
・土壌を膨軟にしておいて注入する。
・降雨直後は処理しない。
・石灰類や石灰窒素等は土壌消毒後、作付け前に施用する。
・苗木が徒長かつゴボウ根となるので窒素肥料を控え、初秋に根切りをする。 |
30倍液
1㍑/m2 |
ジョーロを用い床面に均一に灌注する。
灌注後の処理は上記と同じ。 |
クロルピクリン燻蒸剤
ドジョウピクリンドロクロール |
原液
30cc/m2
(注入) |
| 注入量 |
1穴当り3cc、
注入後、穴を踏み固めて塞ぐ |
注入後の処理はNCSと同じ |
ネキリムシ等の防除法(蒔き付け、床替前)
| 薬剤 |
使用量(m2) |
処理法及び注意 |
トクチオン微粒剤F
ダイアジノン粉剤(2%)
ダイアジノン微粒剤F(3%)
バイジット粒剤(5%) |
6~12g
10~15g
5~10g
9~12g |
・何れも均一に散布後、深さ10cmくらいの範囲の表土とよく混和する。
・使用にあたってはゴム製手袋を着用する。
・ダイアジノンは地温が10~15℃以上で無いと効果が出ない。 |
|
発芽促進処理法
| 樹種 |
処理法 |
共通事項 |
| スギ |
浸水15℃ 24時間 流水浸漬7日間 |
24時間浸水後低温処理0℃1ヶ月
2~3日間清流浸水漬
湿った種を5度前後で約1週間冷却 |
| ヒノキ |
冷水浸漬1℃ 24時間※ |
| マツ |
低温処理5℃ 1~2ヶ月 |
※桶などの適当な容器を用い、氷または雪が溶解した場合の水量に十分浸漬しうる見込み量の種を布袋に詰め、氷または雪の間に入れて、一昼夜放置する。
種はその間に漸次融水中に浸漬冷却させる。
浸漬の済んだ種は、蒔き付けに支障の無い程度に陰干ししてなるべく早く蒔き付ける。
|
種の消毒法
| 方法 |
薬剤 |
処理法 |
| 浸漬法 |
チウラム・チオファネートメチル剤
(ホーマイ水和剤) |
200倍液に30分浸漬する。
種を木綿袋に入れて浸漬した後、水洗いをし陰干しして蒔き付ける。 |
| 粉衣法 |
チウラム・チオファネートメチル剤
(ホーマイ水和剤:水和剤を粉態のまま使用する)
チウラム剤 |
種1kgに対し、チウラム・チオファネートメチル剤は10g、チウラム剤は2~5gをまぶす。
その方法は陰干しした種と薬剤を同時に、缶ないしは箱等の容器に入れてよく振れば容易に粉衣出来る。 |
Topへ
|
種の蒔き付け量の計算例
| 樹種 |
➂発芽率% |
①
1gの粒数 |
②
純量率 |
④
成苗率 |
⑤
保残率 |
⑥
仕立本数 |
備考 |
| 45 |
40 |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
| スギ |
(1) |
19.5 |
21.9 |
25.1 |
29.2 |
35.1 |
43.8 |
58.5 |
87.8 |
300 |
95 |
60 |
50 |
750 |
|
| (2) |
8.5 |
9.5 |
10.9 |
12.7 |
15.2 |
19.0 |
25.3 |
38.0 |
300 |
95 |
66 |
700 |
500 |
|
| (3) |
9.7 |
11.0 |
12.5 |
14.6 |
17.5 |
21.9 |
29.2 |
43.9 |
300 |
95 |
50 |
80 |
500 |
|
| ヒノキ |
(1) |
15.6 |
17.6 |
20.1 |
23.4 |
28.1 |
35.1 |
46.8 |
70.1 |
400 |
95 |
60 |
50 |
800 |
|
| (2) |
10.5 |
11.8 |
13.5 |
15.7 |
18.8 |
23.5 |
31.4 |
47.1 |
400 |
95 |
65 |
70 |
800 |
|
| (3) |
9.5 |
10.7 |
12.3 |
14.3 |
17.2 |
21.5 |
28.6 |
43.0 |
400 |
95 |
50 |
60 |
500 |
|
| 樹種 |
➂発芽率% |
①
1gの粒数 |
②
純量率 |
④
成苗率 |
⑤
保残率 |
⑥
仕立本数 |
|
| 45 |
40 |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
| アカマツ |
8.7 |
9.0 |
9.7 |
10.3 |
11.1 |
12.0 |
13.0 |
14.2 |
100 |
95 |
70 |
500 |
|
| クロマツ |
13.2 |
|
14.8 |
|
17.2 |
|
19.8 |
|
75 |
95 |
70 |
600 |
|
計算式
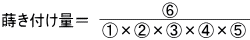
スギ(2)間引きを加算しない、スギ(➂)間引きを見込んだ場合
ヒノキ(2)(3)間引きを加算せず。
|
病害虫薬剤駆除法
スギ赤枯れ病・マツ葉枯れ病の防除薬剤と散布法
| 薬剤 |
濃度 |
散布量 |
散布時期 |
展着剤の可用等 |
| 石灰ボルドー液 |
4-4式~6-6式 |
m2当り
200~300cc |
5月中旬~10月中旬
2週間おきに10~12回
梅雨期・台風期には間隔を短縮する。 |
・湿展性展着剤(リノー、グラミン等)を10㍑あたり2cc添加する。
・少数回散布法
マンネブ剤、マンゼブ剤、プロピネフ剤にPVA(ポリビニールアルコール)、または、パラフィン系固着剤を薬液1㍑に10cc添加した場合は、1ヶ月おきに6回散布で良い。 |
マンネブ剤
(マンネブダイセンM) |
水和剤
400倍液 |
マンネブ剤
(ジマンダイセン) |
プロピネル剤
(アントラコール) |
石灰ボルダー液は、アカマツに対し薬害を及ぼすことがあるので散布してはいけない。
PVAには、「ゴーセノール」、N-300C-500、パラフィン系固着剤には、「ステッケル」がある。
|
生育期の主要病害虫と薬剤防御法
| 病害虫名 |
被害発生時期 |
被害苗木 |
防除法 |
| 立枯病 |
倒伏型5~6月
根腐型7月以降 |
スギ、ヒノキ、マツ稚苗 |
リゾクニア菌による発病の場合は、PCNB剤(ペンタゲン水和剤)1,000倍、フザリウム菌の場合はタチガレン液剤500倍液を3㍑/m2を如雨露で床面に灌注する。 |
| クモの巣病 |
6~7月
9~10月
長雨が降る時期 |
主としてスギ、ヒノキ、マツ稚苗 |
・発病を認めたら、直ちにパリダマインシン剤(パリダマイシン液剤)の600~1,000倍液を羅病部を中心に300cc/m2を床面が濡れる程度に散布する。
・予防散布
多雨時期に銅剤(4-4式ボルドー液、銅水和剤)、またはマンネブ剤の500倍液を200cc/m2散布する。
ただし、マツには銅剤は不可。 |
| ペスタロチア病 |
6~10月 |
ヒノキ苗に多発
スギ、マツ苗にも発病 |
チオファネートメチル剤(トップジンM水和剤)、ベルミル剤(ペンレート水和剤)の1,000から2,000倍液を、強風などで苗木傷んだ直後に散布する。 |
根切虫
(コガネムシの幼虫) |
4~10月 |
スギ、ヒノキ、マツ苗 |
夏期防除のため、7月下旬~9月に薬剤防御を行う。
・バイジット粒剤を9~12g/m2 、または、プロチオホス剤(トクチオン微粒剤F)を6~12gm2、苗木に散布し、土壌に鋤込む。
・バイジット乳剤1,000倍液を1m22㍑如雨露で土壌に灌注する。 |
ヨトウムシ
(カブラや蛾の幼虫) |
5月下旬~10月 |
スギ、ヒノキ、マツ苗 |
ディプテレックス粒剤1~3g/m2、NAC粒剤(デナポン)3~6g/m2、DEP粒剤(ネキリトン)1~3g/m2を散布する。 |
| ウリハムシモドキ |
6月下旬~9月上旬 |
ヒノキ苗 |
スミチオン乳剤1,000倍液を6月下旬~7月に1~2回散布する。 |
| スギノハダニ |
4~10月 |
スギ |
・発生を見たら、ネオサッピラン、アカールCMP等の1,000~1,500倍液を10日おきに数回散布する。
・発生を見たら、ジメートエートを1,000~1,500倍液を30日間隔に散布する。
・ジメートエート5%粒剤8~10g/m2を苗間に散布し、土壌に鋤込む。 |
|
間引きの要領
| 回数 |
時期 |
スギの場合 |
間引き予定本数に
対する間引き割合 |
対象苗 |
| 1 |
梅雨の初め
6月上旬 |
苗長3cm |
40% |
過密部分の調節、発育不良苗、被害苗、形質不良苗 |
| 2 |
7月中旬 |
枝2~3本 |
30% |
同上 |
| 3 |
8月上~中旬 |
|
30% |
上記の他、生長遅れの苗、徒長苗、予備苗 |
※苗木はかなり根を張った頃は、間引きは抜き取らず、摘み取る法が良い。
最終仕立本数(1m2当り)
| スギ |
ヒノキ |
アカマツ・クロマツ |
| 500~600本 |
600~700本 |
450~600本 |
Topへ
|
欠乏症の検索表
| 症状 |
欠乏症 |
欠乏した状態 |
| 主に老葉(下葉)から現れる。 |
普通、植物全体に現れる |
窒素欠乏症 |
全体(幹、枝葉)に生育が不良となる。
葉は下方の古い葉より淡緑色~黄緑色となり、次第に上方に及ぶ。
初期に欠乏が起こると茎は短く、細くなる。
根の育成も悪い。
窒素は体内を移動しやすいので、まず古い部分のものが新葉部に移動し、古い葉から欠乏症状が現れる。 |
| 燐酸欠乏症 |
葉は、濁った暗緑色を示し、また紫色から赤紫色を帯びる。
欠乏が著しいときは下葉は黄変し,矮性となる。
根の発達、特に根の分岐が悪くなる。
根の発達も不十分で細根の出方が少ない。
-スギ・ヒノキ-
新梢の発育を停止し、幹は緑褐色を呈し、葉は帯紫暗緑色を呈する。
スギ蒔き付け苗では、発芽後45日頃から下葉の先が青銅色となり、段々進むと古銅色となる。
-アカマツ・クロマツ-
頂芽を除き、下葉より暗紫色となる。
蒔き付け苗では、発芽後45日頃から下葉の先の方から暗紫色となり、8~9月頃に赤褐色または、赤紫色を呈する。 |
| 普通、老葉(下葉)に現れる。 |
加里欠乏症 |
古い葉の葉脈の間や葉先の周辺部に黄~褐色の斑点を生ずる。
茎葉細く、葉は時に下方に曲がる。
欠乏が酷いときと植物全体が黄化する。
欠乏初期は、葉が暗色がかった青緑色または、濃緑色を呈し、窒素を与えすぎたような色になるが、それほど伸びず、なんとなく弱々しく、そのうち下葉が茶褐色となる。
苗畑では、外観的な症状はほぼ見られない。ただし、枝葉を触ってみて、柔らかい感じのスルモノは一般に加里が少なく、窒素や水分が過剰な場合が多い。
-スギ・ヒノキ-
暗緑色~淡黄色となり下葉に赤みを帯びる
-アカマツ・クロマツ-
暗緑色~淡黄色となり頂芽は萎縮する。
|
| 苦土欠乏症 |
下葉から黄色~褐色~赤色となり、次第に上方に及ぶ。 |
| 主に新葉(芽葉)に局所的に現れる。 |
若い葉の先端、または基部が変形し、やがて頂芽が枯死する。 |
石灰欠乏症 |
成長点の活動が弱まり、頂芽の部分は釣鐘状に曲がり、やがて枯死する。
他の要素に比べ、欠乏症は現れにくいが、スギでは根の発育及び発根が阻害され、頂芽・側芽とも伸長を停止し、枯死する。 |
| 硼素欠乏症 |
頂芽の幼葉の基部が淡緑となり、やがてここから枯れ出す。 |
| 新葉は枯死すること無く、黄色~白色に褪色し、時に萎凋する。 |
鉄・マンガン欠乏症 |
一般的に黄化現象(クロロシス)が現れ、時にこれに伴う死壊組織が発生する。
葉緑素の生成が妨げられ黄化現象が現れる。
特にスギ・ヒノキに起きやすい。
スギ・ヒノキ・アカマツでは、新梢の部分から黄色~黄白色を呈し、次第に下部に及ぶ。 |
要素欠乏症の対策
| 窒素 |
施肥の改善 |
有機質肥料の増施、堆肥は完熟したものを施す。
善良を元肥とせず、適時追肥、特に砂質土壌では数回に分施 |
| 葉面散布 |
尿素、ヨーゲン0.25~0.5%、1m2当り300~600cc 5~7日おきに数回 |
| 土壌追肥 |
速効性の尿素、硫安、塩安、液肥等(ただし原則として7月下旬まで)
水肥とする場合、濃度0.5%以下、尿素100~200倍、硫安・塩安50~100倍 |
| 燐酸 |
施肥の改善 |
燐酸吸収力の強い土壌では、過石は堆肥に混用。
また溶成燐肥、トーマス燐費等枸溶成肥料と併用。
基肥としては根に最も吸収されやすい位置に施す。
燐酸は苦土とは吸収と利用において相助性を持つので苦土と併用すると良い。 |
酸性土壌の改善
焼土 |
不可給態燐酸の有効化 |
| 追肥 |
燐安液肥(7-20-0)を早急に追肥、蒔き付け苗スギ、ヒノキ200倍、アカマツ300倍 |
| 葉面散布 |
燐酸塩0.5%液 1m2当り300~600cc 7~10日おきに散布 |
| 加里 |
施肥の改善 |
窒素をやり過ぎないこと。
加里肥料及び加里を含む有機質肥料を不足しないよう与える。
加里の吸収最盛期(8~10月)の間に追肥(9月上~中旬)
冷害の起こるような年には加里欠乏が促進されるので加里を増施する。 |
| 土壌改良 |
過湿状態の苗畑では排水、砂質土壌では腐植の増加を図る。 |
| 石灰 |
施肥の改善 |
有機質肥料、特に堆肥類の増施・窒素と加里の過用を避ける |
| 石灰質肥料の適量施用 |
消石灰、炭カル、珪カル、苦土石灰 |
| 石灰含有肥料の施用 |
石灰窒素、焼成燐肥、熔成燐肥、草木灰等 |
| 苦土 |
施肥上の配慮 |
基肥に苦土肥料の施用・・・・・熔成苦土燐肥(20%)、苦土石灰(28%)、硫酸苦土(20~28%)、水酸化マグネシウム(50~60%)、堆肥・草木灰
標準施用量・・・・・10g当り熔燐38~56kg、苦土石灰57~75kg、水酸化マグネシウム(60%)19kg
有機質肥料の増施、酸性土壌の改良 |
| 拮抗要素の調節 |
加里、石灰の過用を避ける。 |
| 葉面散布 |
葉色が黄桃色になり始める初夏の頃、硫酸苦土2~3%液(水18㍑に315~463g)を3回位散布。 |
鉄
マンガン
硼素 |
中性~アルカリ性化の防止 |
石灰の過用を避け、塩基性肥料の施用に注意。 |
| 土壌反応の矯正 |
中性~アルカリ性になった土壌に対し、硫黄粉を10g当り150~250kg施用または酸性肥料の施用。 |
| 土壌改良 |
天地返し、焼土、湛水(Feの有効化) |
| 各要素含有肥料等の施用 |
堆肥 3,000kg 焼土3,000~5,000kg
(施用量は10a当り)熔成微量要素複合肥料(ETE、ミネラス、ミネリッチ)3~4kg
| Fe・・ |
赤土1,500kg、肥鉄土1,000kg、硫酸鉄・塩化鉄3.75kgを堆肥と混用 |
| Mn・・ |
成分量として950~1,900g(硫酸マンガン、熔成マンガン等) |
| B・・ |
硼砂肥料、硼酸肥料 |
|
| 葉面散布 |
硫酸第一鉄、塩化第二鉄の0.1~0.2%(水18㍑に18.8~37.5g)
硫酸マンガン0.2~0.3%(水18㍑に37.5~46.3g)各1週間おきに2~3回散布 |
|
堆肥製造法
| 添加材料 |
|
石灰乳
消石灰50kgを約1,000㍑の水に溶かしたもの |
|
硫安
15kg
(または、鶏糞100kg) |
|
硫安
5kg
(必要あれば) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
→ |
|
一夜
→ |
|
約2
週間
→ |
|
3~
4週間
→ |
切り返し
(2回目積み替え) |
切り崩し
水掛け
窒素の添加
積込
覆蓋 |
|
2~3
週間
→ |
|
| 注水量 |
|
340㍑前後 |
|
約470㍑ |
|
1400㍑ |
|
稲藁 約240㍑
麦藁 約380㍑ |
|
|
| 摘要 |
|
切断した藁を水槽に付けても良い |
|
40~50cm積む毎に、石灰乳と水を注加し踏圧することを繰り返し、堆積する。
蓋は、古俵、コモ、筵、藁束等 |
|
注水量は堅く握って水の滴る程度。
窒素は積込中に粉のまま散布。
積込の高さは、1.8m(稲藁)
2.0m(麦藁) |
|
本積中内部にあったものを外側に積む。
外側にあったものは、内部のものと混和して内部に積み込む |
|
熟成に要する日数は材料、気温等の条件によって異なる。 |
(注)藁1,000kgから生産される堆肥の標準量 稲藁1,500~2,000kg 麦藁2,000~2,500kg
|
|
耕耘時の生藁鋤込み法
| 1.施用量 |
10a当り500~1000kg三つ切りか裁断して施用 |
| 2.腐熟促進策 |
石灰窒素を10a当り50~100kg(標準60kg)施用
ただし、前作に窒素を多施してある場合は2~3割減らす。
秋施用した場合、翌春に残る窒素量は6~7割と見做されるので、窒素の施肥量はそれだけ減ずる。 |
| 3.鋤込み時期 |
秋が最も良い。春作付け間近の施用は絶対避ける。 |
| 4.鋤込み上の注意 |
①耕運機具の種類によって藁の長さの量を変える。
・トラクターによるロータリーやディスプラウの場合は藁は15cmくらいに裁断する。
・小型機によるロータリーの場合は施用量を500kgに留める。
量を多いと刃が滑って不利。
・鋤起こしによって反転する場合は長いままが良い。 |
| ②重粘土状の場合は、長いまま鋤込み、藁が部分的に表面に出来ているときは春先早めにもう一度耕耘して藁と土をよく混ぜる |
苗木と土壌酸性度・石灰施用による酸性土壌の矯正
苗木と土壌酸性度
| 酸性土壌に対する抵抗性 |
| 強← |
中 |
→弱 |
| クロマツ・アカマツ> |
|
|
|
ヒノキ>スギ |
|
| 主要樹種の好適PH(塘) |
スギ |
ヒノキ |
アカマツ |
カラマツ |
| 5.4~6.2 |
5.0~5.6 |
4.8~5.6 |
5.2~5.8 |
石灰施用による酸性土壌の矯正
| 区分 |
腐植に乏し5%以下 |
腐植に富む5~10% |
腐植がすこぶる富む
10~20% |
腐植20%以上 |
| 砂土 |
56 |
112 |
150~225 |
|
| 砂壌土 |
112 |
169 |
225~300 |
|
| 壌土 |
169 |
225 |
300~375 |
|
| 埴壌土 |
225 |
281 |
375~450 |
|
| 埴土 |
281 |
338 |
450~525 |
|
| 腐植土 |
|
|
|
450~750 |
1.消石灰、炭酸苦土を用いる場合は、上記の数値のそれぞれ0.74掛け、0.84掛けとする。
2.一度に大量の石灰を施すと石灰の過剰障害を起こすので注視する。
(1回に施す消石灰量は10a当り約200kgが限度と言われている。)
| 石灰所要量の計算式 |
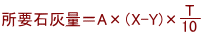 |
|
Aはphを1だけ中性に変化させるに要する炭酸石灰量(または他の石灰量)
Xは改良しようとするPh
Yは改良前のPh
Tは改良しようとする土壌の深さ(cm) |
Topへ
|
発達促進
インドール酪酸(IBA)によるスギ・ヒノキの発根促進処理
| 薬剤名 |
有効成分 |
使用濃度 |
処理法 |
備考 |
IBA
オキシベロン液剤 |
0.4% |
100ppm |
溶液中に挿し穂の基部3cm位を24時間浸漬した後、挿し付ける。 |
40倍相当 |
IBA
オキシベロン粉剤 |
1.0% |
1% |
粉剤を差しの基部約1cmに粉衣し、軽く振って余部の粉末を落として挿し付ける。 |
|
(注) 溶剤は同一溶液を2~3回使用できる。但し、変質ものは不可。
処理容器は金属製のものは不可。処理場所は日陰、静穏で乾燥の強くないところ。
水溶液は太陽光線に晒すと褐色となり、沈殿を生じ効果が減衰するし、水溶液の状態では効力が早く落ちる。
溶液の保存は着色瓶または不透明の容器に入れ凍らない程度の低温で行う。
|
苗木規格(島根県)
| 樹種 |
幼苗 |
山行苗 |
備考 |
| 区分 |
長さ
(cm) |
根元径
(mm) |
苗齢
(年生) |
長さ
(cm) |
根元径
(mm) |
| 挿し木スギ |
|
|
|
2 |
35~65 |
6.5 |
1.無病健全で苗型が整っていること。
2.山行苗は、比較苗高(苗高/根元直径)70以下を目安とする。かつ、根系が良好であること。(スギとヒノキの場合)
3.根元直径は幹の地際の直径
4.産地系統等を明示した表示票を添付すること。 |
| 実生スギ |
大 |
12~25 |
1.5 |
2 |
35~60 |
6.0 |
| 中 |
8~12 |
|
3 |
35~65 |
8.0 |
| ヒノキ |
大 |
12以上 |
1.0 |
2 |
35~60 |
5.0 |
| 中 |
8~12 |
|
3 |
35~65 |
6.0 |
| アカマツ |
大 |
12以上 |
2.0 |
2 |
20以上 |
6.0 |
| 中 |
8~12 |
|
|
|
|
| クロマツ |
大 |
10以上 |
2.5 |
2 |
20以上 |
6.0 |
| 中 |
6~10 |
|
|
|
|
| クヌギ |
|
|
|
|
|
8.0 |
幼苗及び山行苗の大きさ、形態の期待値
| 樹種 |
苗齢 |
苗高
(cm) |
根元直径
(mm) |
生重量
(g) |
比較苗高 |
G/H率 |
スギ
(実生) |
1-0 |
12~18 |
2.0< |
3.5< |
50~60 |
1.7~2.0 |
| 1-1 |
35~45 |
7.0< |
70< |
| 1-1-1 |
45~55 |
10.0< |
90< |
| ヒノキ |
1-0 |
10~16 |
1.5< |
2.0< |
55~65 |
1.3~1.5 |
| 1-1 |
35~45 |
6.0< |
45< |
| 1-1-1 |
40~50 |
8.0< |
60< |
| アカマツ |
1-0 |
12~16 |
2.5< |
4.0< |
30~40 |
2.0~3.0 |
| 1-1 |
25~35 |
7.0< |
50< |
| クロマツ |
1-0 |
10~14 |
3.0< |
5.0< |
25~35 |
2.5~3.5 |
| 1-1 |
20~30 |
8.0< |
60< |
比較苗高は、苗高÷根元直径
G/H率は、生重量÷苗高
|
参考資料:山行苗輸送標準積載量(6トン積トラック)
| 樹種 |
苗齢 |
苗高
(cm) |
積載量
(千本) |
参考県 |
スギ
(実生) |
3 |
45 |
27 |
茨城県 |
| 3 |
45 |
24~25 |
神奈川県 |
| 2 |
35~55 |
50 |
福岡県 |
| 2 |
35~45 |
50~60 |
高知県 |
| 挿し木 |
1 |
35~55 |
55 |
福岡県 |
| ヒノキ |
3 |
45 |
36 |
茨城県 |
| 3 |
45 |
25~30 |
神奈川県 |
| 3 |
45 |
45 |
福岡県 |
| 2 |
35 |
60 |
福岡県 |
アカマツ
クロマツ |
2 |
25 |
75 |
茨城県 |
| 2 |
30 |
30~36 |
神奈川県 |
| 2 |
20~25 |
70 |
福岡県 |
|
苗畑の土壌管理
苗畑土壌の簡易鑑定結果による診断基準
| 項目(性質) |
良い土壌 |
悪い土壌 |
| Ph(KCL) |
6.0~5.2 |
4.0以下 |
| 置換性(有効)石灰 |
200mg(0.2%)以上 |
100mg(0.1%)以下 |
| 置換性(有効)加里 |
15mg以上 |
8mg以下 |
| 置換性(有効)苦土 |
25mg以上 |
10mg以下 |
| 有効燐酸 |
10mg以上 |
2mg以下 |
| 塩基置換容量(保肥力) |
10me以上 |
5me以下 |
| 燐酸吸収係数(固定力) |
700~1500 |
1500以上または700以下 |
| 活性アルミナ |
10mg以下 |
20mg以上 |
土壌管理
| ねらい |
主な管理法 |
| 土壌の理化学性の改善 |
①深耕、秋耕、心土耕、混層耕・天地返し
②客土
➂焼土
④堆肥など有機物または土壌改良剤の施用
⑤土壌反応の矯正 |
| 土壌水分の適正保持 |
①排水
②灌漑
③客土による耕土の嵩上げ
④有機物施用による保水力強化 |
| 浸食(水蝕)の防止 |
①地表の被覆(敷藁など)
②等高線畝立、投稿帯状耕作、階段耕作
③誘水溝の設置
④堆肥など有機物、土壌調整剤の施用(土壌改良による雨水の浸透促進) |
| 連作障害の回避 |
①輪作(地力維持増進作物との組み合わせ)
②休閑(緑肥栽培とその利用) |
|
Topへ
|
|
除草剤の標準的施用法
施用
区分 |
除草剤 |
10a当り1回の施用量 |
初回の
施用時期 |
施用間隔
(回数) |
散布要領 |
| 蒔き付け床 |
床替床 |
| 単用 |
シマジン水和剤 |
100~200g |
200~300g |
・蒔き付け床
5月下旬頃
床替床活着後
・蒔き付け床
覆土直後
・床替床
床替後1週間以内 |
30~50日
(3~4回) |
10aあたり180~200㍑の水に除草剤を溶かして、低圧噴霧器で土壌の表面に均一に散布する。 |
| ゲザミル水和剤 |
100~200g |
200~300g |
30~45日
(3~4回) |
| MO乳剤 |
1,000~2,000cc |
1,200~1,500cc |
25~30日
(3~4回) |
| ロンスター水和剤 |
100~200g |
250g |
20~30日
(3~4回) |
| トレファノサイド乳剤 |
200~300cc |
300~400cc |
30~45日
(3~4回) |
| サターン乳剤 |
600cc |
800cc |
30~40日
(3~4回) |
混用
(例) |
MO乳剤
ゲザミル水和剤 |
1,000cc
50~100g |
1,100cc
100g |
同上 |
30~45日 |
同上
溶解はケザミルを先にし、その中に他の除草剤を混入する。 |
サターン乳剤
ゲザミル水和剤 |
500cc
50g |
600cc
100g |
注意事項
①除草剤が移動しやすい砂土から砂質壌土あるいは水分の多い土壌に対しては、この標準量を減らすか、分施する。②雑草の種類に応じて最も適した除草剤を選択施用、または混用する。
➂シマジンは、蒔き付け床ではスギ、ヒノキには使用しない。
マツに対しても苗木が3~⑤cmに成長してからが安全である。
④ヒノキの蒔き付け床(初期)にはサターン乳剤が最も安全である。他の薬剤は初生葉期に薬害を及ぼすことがある。
⑤蒔き付け床では、発芽直後の苗木が軟弱な時期には施用を避ける。
⑥これらの除草剤は大きくなった雑草には効かない。5mm以上の草を除去後、施用する。
⑦これらの除草剤は、土壌中に適度の水分があるときに有効に働くため、適量の降雨後に施用するのが望ましい。
従って、大雨や長雨直後の過湿な時や、旱天続きで過乾な時には施用しない。
⑧施用後条件が良ければ、地表下1~2cmのところに除草剤の処理層が形成、保持されているから、残効期間(ほぼ施用間隔日数)は中耕等、地表を動かすようなことはしない。
※どの雑草に効能があるか纏めること
|
|
苗畑除草剤が効く草
|
MO乳剤 |
トレファノサイド乳剤 |
シマジン、ゲザミル |
サターン乳剤 |
| イネ科 |
メヒシバ
アキメヒシバ
オヒシバ
ノビエ
ニワホコリ
スズメノカタビラ
スズメノテッポウ
エノコログサ
イヌビエ |
メヒシバ
アキメヒシバ
オヒシバ
ニワホコリ
スズメノカタビラ
スズメノテッポウ
エノコログサ
イヌビエ |
|
ヒメシバ
アキメヒシバ
スズメノカタビラ
ニワホコリ
オヒシバ
カルカヤ |
| その他 |
カヤツリグサ
ヒデリコ
テンツキ
ザクロソウ
スベリヒユ
カタバミ
タデ
ツユクサ
アゼナ
アゼトウガラシ
トキワハゼ
ムラサキサギゴケ
イヌビエ
アゼムシロ
エノキグサ
等 |
ザクロソウ
スベリヒユ
イヌビユ
アオビユ
カタバミ
ハコベ
ノミノフスマ
ツユクサ
ムラサキサギゴケ
アゼナ
アカザ
シロザ
タデ類
等 |
カヤツリグサ
ヒデリコ
テンツキ
トキンソウ
アレチノギク
ヒメムカシヨモギ
ヒメジヨン
ハハコグサ
ザクロソウ
スベリヒユ
ツユクサ
ノミノフスマ
コニシキソウ
エノキグサ
アゼナ
アゼトウガラシ
アゼムシロ
ムラサキゴケ
イヌフグリ
ムシクサ
トキワハゼ
キカシグサ
タデ類
等 |
カヤツリグサ
スベリヒユ
イヌビユ
ツメクサ
カタバミ
エノキグサ
コニシキソウ
ムラサキサギゴケ
トキワハゼ
アゼトウガラシ
アレチノギク
ヒメジョオン
ヒメムカシヨモギ
トキンソウ
スズメノトウガラシ
アゼナ
等 |
|
|
|
雪害対策(応急的な方法)
(1)機械的(雪圧による)雪害防除法
①越冬苗木は積雪前に掘り起こして、斜め仮植をすると防げる。ただし、積雪かでの衰弱に加え、雪腐れ病に冒される危険があるため、仮植は薄めに丁寧に行い、かつ雪腐れ病対策を十分に行う。
②採穂台木は支柱(1本または3本)を立て、枝葉を絞って縄で巻き締める。
(2)雪腐れ病防除法
①雪解け時期の苗床の水はけを良くするため、積雪までに排水溝を作っておく。
②やむを得ず越冬仮植する場合はなるべく早い時期に行い、苗木は粗く並べ入念に仮植する。
③越冬苗木に対しては、予防用薬剤を散布する。
④積雪期間が長引くようであれば、雪上に、黒土、木炭粉末、木灰、焼き籾殻、黒色クレモナ、寒冷紗を散布または被覆するか、雪面に畝立てをして融雪を促進する。
凍害・寒害対策(応急的な簡易方法、霜柱対策も含む)
(1)苗木または地表の被覆
①葦簀、コモ、筵、寒冷紗または日覆材料を用い、南を高く北を低く屋根覆いをする。
②常緑樹の枝、笹などを床面に立てる。
③藁、カヤ、落葉等を苗木が隠れる程度に直に被せる。
④苗木の間の地表面に落葉、鋸屑、籾殻、粉炭等を敷く。(霜柱防止)
(2)苗木の仮植または貯蔵
①苗木を掘取り、松林下など上層に遮蔽物がある場所に深めに丁寧に仮植する。
②掘り取った苗木を屋内の土間に仮植貯蔵するか、半地下式の室、横穴式の地下貯蔵庫等にコモ包みのまま貯蔵する。
(3)結氷または気温冷却防止
燻煙法、灌水法(灌漑法)、散水法がある。詳細は、「作物気象災害対策指針」を参照
|
|
|
|
| Topへ |