
⑧林業経営を始めよう
| はじめに | 樹種の種類 | 苗木から植栽 | 植栽から保育 | 間伐から主伐 | 伐採・搬出 | 林道管理 | 安全対策 | レクリエーションの森 | メモ |
| はじめに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【人工林経営と天然林経営】
人工林経営 -地位- 人工林造成に適した土地とは、土地の地位(生産力)が高く、その場所での作業性が良いところです。 地位は、Ⅰ~Ⅴまで区分され、人工林に適した地位は、Ⅰ~Ⅲ。 林齢と樹高曲線の関係から皆伐前に樹高を測定してから決める。 地位Ⅰ 人工林施業に適している 地位Ⅱ 人工林施業に適している 地位Ⅲ 人工林施業に適している 地位Ⅳ 人工林施業も可能。但し収益性は悪い 地位Ⅴ 人工林施業に属さない 地域によって異なるが、40年生で樹高が、地位Ⅰ(19.4m以上)、地位Ⅱ(15.6m以上)、地位Ⅲ(11.9m以上)と区別しているところもある。 -地利級- 作業性のことを地利級といい、植栽や下刈り、除伐、間伐等の保育作業、主伐による搬出などの作業が容易に行うことが出来るかの情報が経営を行う上で重要です。経費がどれくらい掛かるかは、林道や作業道からどれくらい離れているかで大きな影響を受けます。このため、道からの距離を指標として利用します。 地利区分の一例
-不成績林- 造林に適さない土地として、以下の様な基準(例)がある。なお、場所によって、数値は異なる。 ・成立本数が標準の6割未満の林分 を不成績林とする。 ・うち4割未満の林分を生育困難地とする。 ・積雪深が2.5m以上 ・標高1400m以上 ・傾斜45度以上 -植林のゾーニング- 日本の林業の失敗は、拡大造林時に後先考えずに植えるだけ植えた事です。このため、地形や地利を考えながら、植林する必要があります。以下の図は、タワーヤーダを使うことを前提としたゾーニングです。 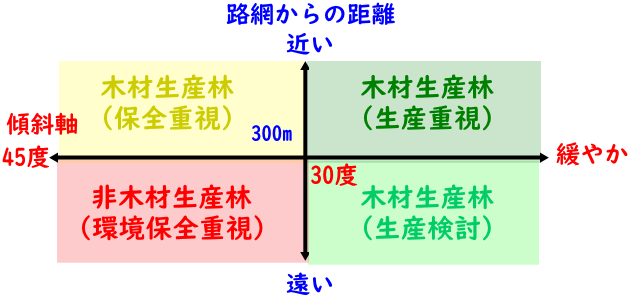 造林地に適さないと地上権の場所には、植林を行わない勇気が必要です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【樹木の選定】 -適地適木- その土地の環境条件(温度、地形、土壌、気象)に最も適した樹種を選定する。 自然災害(風害、雪害)を考慮する。 忌み地など不適地に植栽すると、成長不良や病害虫リスクの増大が発生し、林地荒廃の要因となる。 広葉樹は適地の範囲が狭いため、周囲の状況に合わせる必要がある。 -経済性- 適地適木となる樹種が複数あった場合は、木材として販売する際に最も高く売れる可能性が高い樹種を選択する。 一定以上の径級に達しないと利用価値が低く、径級別に材積単位で価格が決定するため、材積を稼ぐ品種を選ぶ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然林経営 -天然下種更新- ・地表を掻き起こしして、周辺に生育する母樹の種子を散布させて更新をはかる方法。 ・目的の樹種の稚樹を育てる方法 -萌芽更新- ・萌芽能力のある太さで伐採し、萌芽で育てる方法。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||