
⑧林業経営を始めよう
| はじめに | 樹種の種類 | 苗木から植栽 | 植栽から保育 | 間伐から主伐 | 伐採・搬出 | 林道管理 | 安全対策 | レクリエーションの森 | メモ |
| 育種の考え | 苗木調達の仕組み | 林業品種 | 種子の確保 | 苗木作り | メモ | ||
| 苗木から植栽:苗木調達の仕組み |
||||||||||||||||||||||||||||||
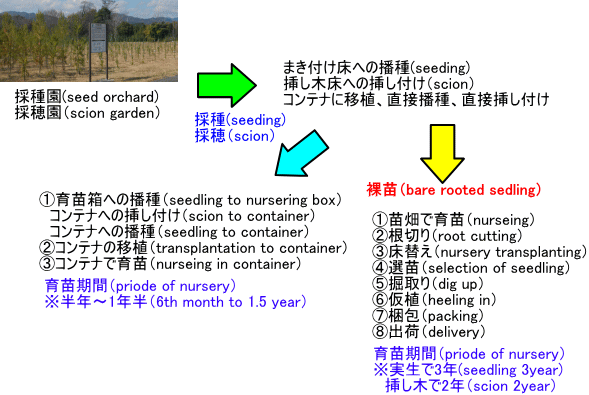 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.種子の生産 林業種苗法(昭和45年法律第89号)における「種苗」とは、林業の用に供される樹木の繁殖の用に供される種子、穂木、茎、根及び苗木(幼苗を含む)であって、政令で定める樹種(スギ、ヒノキ、アカマツ、クロマツ、カラマツ、エゾマツ、トドマツ、リュウキュウマツ)となっている。 ①林業用の種子 国が定めた要綱(林業用優良種苗生産需給調整要綱 昭和36年9月9日36林野造第2817号林野庁長官より道府県知事あて)によると、都道府県の造林に必要な種子や苗木等の生産は、産地及び系統区分の明らかなものを用い、原則自給とすること、できるだけ県営で行うよう通達している。 ②採種園 林木の種子生産は、採種園という種子採取専用の林で行います。採種園は、遺伝的に優れた種子を計画的かつ大量、安価に生産することを目的とし、原則として造林を行う地域内につくること。 ・通常型採種園 従来方式の種子生産方式。課題として、スギやカラマツでは確実な結実を促すため、3、4年に1度しか種子採取を行えない場合がある。このため、毎年確実に確保するためには、3~4倍の面積を確保する必要がある。 この方式によるスギやマツの種子生産量は、ha当たり30kgを目安とする。 ・ミニチュア採種園 ミニチュア方式は、造成、改廃が容易で、スギでは造成4年後に種子の採取が可能となるうえ、単位面積当たりの種子生産量はha当たり240kgと多く、採種木の樹体が小さいので整枝剪定や収穫時に脚立が要らず、管理作業に危険を伴わない長所がある。
スギ、ヒノキの採種園は、母樹苗木を16000本/haの間隔で植栽し、800本→400本/haへ間伐する。 樹高は3mで断幹し、枝を均等に張らして、樹冠全体に日光が当たるようにする。 自家受粉を避けるため、異なる品種系統が隣接するように設計する必要があり、他品種で交配するようにランダムに配置する。 この方式のデメリットは、毎年の下刈り、病虫害防除の作業が必要。また、球果採取には、高所作業となるため、脚立等の使用が必要となる。管理を忘れると、成長し、樹冠が密閉し採取しにくくなる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.種子及び苗木の性能 林業用品種の種子は、主に県内各地から集めた様々な品種間の相互交配によって得た混合種子で提供する。 この理由は、種子や苗木の遺伝形質を多様にすることで、高い環境適応性をもたせること。また、気象害、病虫害の一斉被害を避けるなど造林上いくつかの有用な効果が期待できる。 このため、農業用と異なり、林業用種苗は、山全体、森林全体を考え、造成する必要がある。 注意事項として、採種園からの種子が必ずしも優れた苗木になるわけではない。 その理由は、種子の遺伝的多様性と、品種そのものが持つ着果結実特性である。このため、着果結実量が著しく多い品種が数種存在すると、形質の受け継ぎ次第では、期待したほど育種効果が得られない可能性が高まる。 このため、苗木を育苗中に形質の悪い物、成長がおかしい物があれば、抜き取って破棄することが優良な苗木を生産する必須条件になります。 ここでは、もったいない精神は捨てる必要があるのです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.種苗配布区域について 林業種苗法(第24条1項)で、スギ、ヒノキ、アカマツ、クロマツについて種苗の配布区域は制限されている。
理由は、種子を生産する母樹の産地の気候風土の違いから起こる不成績造林地の発生を防ぐためと、優良種苗を確保するためです。例えば、日本海側にヒノキを持っていけば、漏脂病にかかるというわけです。 また、県境で区切られているわけではなく、山脈等で区切られています。降雪量の違いです。 拡大版は「種子の確保」「種子の移動」を参照 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.その他 注意点として、林木の自殖苗の多くは成長が不良となること。自殖苗とは、自家受粉で出来る苗のことで、花粉が同じ個体の雌しべに受粉することで、遺伝的多様性の低下に伴う種としての適応力や生存力の低下、有害形質の顕在化など様々なデメリットがもたらされる。針葉樹の造林樹種は、風媒花のため、虫媒花、鳥媒花ではないため、自家受粉にならざるを得ないのです。このため、採種園には、9種類以上の品種を用意する必要があります。
8種類だと、隣接してしまい、駄目な苗を生み出してしまうことになります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||