
②日本の森林は誰のもの
| はじめに | 森林管理 | 国有林の話 | 民有林の話 | 土地問題 | 林政の歩み | 森林・林業に関連する法律 | 税金 |
| 基本情報 | 都道府県有林 | 市町村有林 | 財産区有林 | 個人所有林 | 企業所有林 | 林業普及員制度 | メモ |
| 現状 | 森林経営計画 | メモ |
| 【森林経営計画】 | |||||||||||||||||||||||||
| 森林経営計画とは、森林所有者、もしくは、森林の経営の委託を受けた者(森林所有者が必ずしも計画を立てる能力を持っているわけでは無いため)が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。 この森林経営計画は、所属する市町村長に提出します。 集まった森林経営計画は、その後、市町村森林整備計画に使用されます。そして、更に、各市町村から集まった市町村森林整備計画は、都道府県の地域森林計画に使用されます。更に、国有林の森林計画と結びつけることで、全国森林計画になります。その結果、国の長期的かつ総合的な政策の方向・目標となる「森林・林業基本計画」に結びつきます。 主な記載事項は、 ・森林の経営に関する長期の方針 ・計画対象森林の現況並びに間伐及び主伐の施業履歴 ・伐採(主伐間伐)、造林及び保育の実施計画 ・鳥獣害防止森林区域における鳥獣害の防止の方法 ・森林の保護に関する事項 ・森林の施業及び保護の共同化に関する事項 ・路網整備に関する事項 ・森林の経営の規模拡大及びそのために必要な路網整備等の目標(必要に応じて記載) ・森林の保健機能の増進を図るための公衆の利用に供する施設(森林保健施設)の整備 になります。 提出先は、森林の所有形態によって異なります。
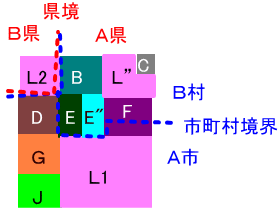 書類の提出先
|
|||||||||||||||||||||||||
作り方の手順
○森林所有者が単独で計画を作成 ○森林の経営の委託を受けた者が単独で計画を作成 ○森林所有者と森林の経営の委託を受けた者が共同で計画を作成 ○複数の森林所有者が共同で計画を作成 ○複数の森林の経営の委託を受けた者が共同で計画を作成 【申請書類】 (1)森林経営計画認定請求書 (2)森林経営計画書 (3)添付書類 ①計画図面(計画対象森林の所在、路網整備等の状況、主伐を行う区域) ②森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面(森林の経営の委託を受けた者が作成する場合に限る。) ③路網整備等につき、森林の土地の所有者の同意があったことを証する書面(他人の土地を利用する場合。) |
|||||||||||||||||||||||||
| 【認定の基準】 市町村森林整備計画(ゾーニング)に合致していることが前提。 チェック項目として、 |
|||||||||||||||||||||||||
| 収穫の保続の基準 | 市町村の独自ルール | 公益的機能別森林施業 | ||||||
| 伐期の延長が望ましい森林 (水源涵養機能の促進) |
山地災害防止、土壌保全、快適環境、保健文化 | |||||||
| 長伐期施業が望ましい森林 | 複層林施業が望ましい森林(非択伐) | 複層林施業が望ましい森林(択伐) | 保健文化機能増進 | |||||
| 特定広葉樹の育成が望ましい森林 | ||||||||
| 主伐 | 適正な林齢での主伐の基準 | 標準伐期齢以上 | 標準伐期齢+10以上 | 標準伐期齢の2倍以上 | 標準伐期齢以上 伐採率の40%以下の択伐 |
|||
| 適正な伐採の方法 | 【皆伐の場合】 伐採跡地が連続して20haを越えないこと |
伐採率30%以下の択伐 | ||||||
伐採後の造林を天然更新による場合
|
||||||||
| 適切な伐採立木材積 | 伐採材積が年間成長量(カメラルタキセ式補正)に相当する材積に5を乗じて得た材積以下 | 標準伐期齢における立木材積が確保されること | ||||||
| 伐採材積が年間成長量(カメラルタキセ式補正)に相当する材積に5を乗じて得た材積の100分の120以下 | 標準伐期齢の立木材積に0.5を乗じて得た材積以上の立木材積が確保されること | 標準伐期齢の立木材積に0.7を乗じて得た材積以上の立木材積が確保されること | ||||||
| 立木材積: 下層木を除いてRy0.75以上 伐採材積: Ry0.65以下となるよう伐採 |
||||||||
| 適正な間伐の基準 | 市町村森林整備計画に定められた間伐の間隔で実施しているか | 単層林の場合 Ryが0.85以上の森林において、Ryが0.75以下になるように間伐しているか |
市町村森林整備計画に定められた間伐の間隔で実施しているか | |||||
| 適正な植栽の基準 | 主伐実施の5年以内に更新が行われているか | |||||||
| 【適切な主伐】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
伐採立木材積の上限(法正林思想)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
隣接する場合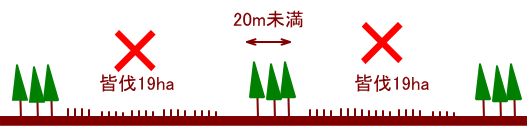 19haが2ヵ所では無く、20ha以下と見做さず、一箇所として扱う。 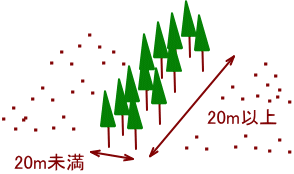 このようなグリーンベルトは、境界として認識されない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主伐量の上限は、成長量の範囲内が基準 ・森林経営計画における主伐量の上限は、森林の成長量を基本として、現況の蓄積が標準よりも多い場合は、より多くの伐採が可能。 ・市町村森林整備計画で「木材生産機能維持増進森林」にゾーニングされている森林は、成長量を1.2倍として計算が可能。 ・天然林など伐採を予定しない森林を計画に加えることにより、その蓄積を活用して主伐上限を増やすことも可能。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
複層林の場合
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【適切な間伐】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工林の場合、0.3ha未満の森林は対象外。 林冠が閉鎖している森林で、5年以内に樹冠疎密度が8割以上の森林 このため、5齢級(25年生)未満の若齢林や、本数調整が終了した老齢林、過密化していない森林、気象害や成育不良で林冠が閉鎖していない森林は、対象外となる。 また、計画期間内に主伐を予定する森林も対象外となる。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※標準伐期齢未満の森林であれば5年以内、標準伐期齢以上の森林であれば10年以内に間伐した場合は基準を適用しない。 間伐下限の計算方法 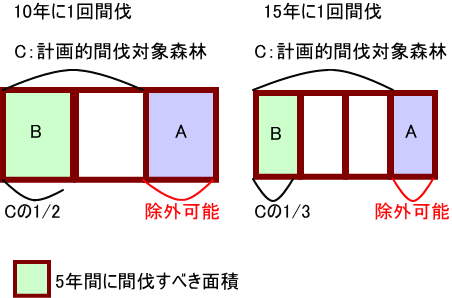
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【植栽】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※2 市町村森林整備計画に適合すると共に、材積伐採率に応じた苗木本数を植えること。 ※3 期待成立本数の3割、または3000本/haのいずれか小さい本数が確保されること これに満たない場合は、2年以内に必要な苗木本数を植栽すること |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【鳥獣害の防止】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
森林経営計画に定められている造林方法が鳥獣害防止森林区域内において当該森林経営計画の期間内に植栽をすることであるときは、鳥獣害の防止のための防護柵の設置、わなその他の方法による鳥獣害の原因となっている鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)その他の当該植栽に係る立木を保護するための措置を実施することとされていること。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
【計画の変更と遵守】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出の内容】 森林経営計画の対象森林で立木の伐採、造林、立木の譲渡、作業路網の設置を した場合に届出書を市町村長等に提出する。 受け取った役所は、•届出書に記載されている事項について、森林経営計画に基づいた施業等を行ったかどうかを確認する。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
【メリット】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||