
⑧林業経営を始めよう
| はじめに | 樹種の種類 | 苗木から植栽 | 植栽から保育 | 間伐から主伐 | 伐採・搬出 | 林道管理 | 安全対策 | レクリエーションの森 | メモ |
| 基本状況 | 針葉樹 | 地拵え | 植え付け | 初期保育 | 枝打ち | 間伐 | 複層林 | 混牧林 | マングローブ |
| 広葉樹 | 地拵え | 植え付け | 初期保育 | 枝打ち | 間伐 | 天然更新 | 混交林 | メモ |
| 保育 | |||||||||||||
| 初期保育として、下草刈り、蔓切り、除伐、雪起こしがある。 |
|||||||||||||
| 下草刈り(下刈り) 日本は、林業に適さない地域にあると言われています。理由は、高温多湿で、陽生植物の繁茂が著しいため、植栽木以上に他の植物が繁茂するからです。 植栽木の生存を保証し、成長を助けるためにも下草刈りは不可欠となります。 一方、北欧や欧州、NZ、半乾燥地では、日本ほど下草刈りの必要性はありません。この他の地域では、下草刈りを軽減するために、陸稲や大豆、蕎麦など、木場作(アグロフォレストリー)をしてきました。 土壌条件の良い場所では、スギ、ヒノキの下刈り期間は5年程度となる。土壌条件の悪いところでは、10年近くかかる場合もある。基本的に、植栽木より周囲の植生が低くなれば、下刈りの必要は無くなる。 下刈りの時期は、土用の丑の頃、(土用の鰻の頃)で、7月下旬~8月上旬となっている。2回実施する場合は、6月下旬~7月上旬と、お盆以降の8月中下旬となる。 道具は、刈り払い機と鎌(柄が短い物と長い物)、機械となる。但し、傾斜地では機械の使用には制限がかかる。 |
|||||||||||||
| 蔓切り 林業では、植栽木の経済的価値を高めるというより、価値を落とさないために、蔓切りをします。 蔓に巻かれると、材の価値が下がるからです。 ・肥大成長が異常になる。→チップ材に利用される ・幹が変形する。 ・蔓が巻き付いた場所が弱点になり、共有や積雪時に折損被害を受ける。 ・樹冠に達すると周囲にも被覆するため、植栽木の成長が阻害される。 ・樹冠を覆った蔓の重みで、植栽木の先端が曲がり、幹が曲がる。 ・樹冠に達した蔓が、周囲の植栽木も同様の被害を与える。 ・草本系の蔓が秋に枯れると、火道になり、林床火災が、樹冠に広がり、大規模火災を招く。 ・伐採時に掛かり木が発生する。「上方よし、つるがらみなし」と大声で言って、伐倒する。
|
|||||||||||||
蔓の種類は、以下の通りである。
蔓は、非常に早く成長する、あっという間によじ登るため、見つけ次第、除去することを心掛ける。 林業地に入る際は、鉈を携行する。鉈で、幹を傷つけないことに留意する。 適した時期は夏頃で、根茎の栄養分が少なくなっている時期のため、再生力が弱い時期である。 根元から切る。場合によっては、鎌や剪定鋏を使用する。 切った蔓は強引に引っ張らない。梢端を傷つける可能性があるため。 植栽木の根元付近にある蔓は、根元で切ると萌芽する可能性があるため、蔓の茎をぐるぐるに巻いて、植栽木から距離を取る方法もある。 つるの切断面に除草剤処理する場合もある。 |
|||||||||||||
| 除伐 形質の悪い樹形の木や目的樹種以外の侵入種を除去する作業。 年間を通じて行う。  やっかいな竹の侵入。竹の伐採、地下茎が伸びないように、板を地面に打ち込むことも重要。 除伐というより、除去。  途中から二股になっている植栽木も除伐の対象です。 |
|||||||||||||
| 雪起こし 雪圧によって倒伏した幼齢木を雪解け直後に起こす作業。縄などで固定して、木を垂直に育てる作業。 雪解け直後に作業しないと、幹の肥大成長が異常となり、幹に傷が付くなど、木材の価値が落ちる。 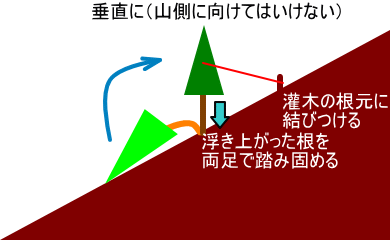 倒れた幼齢木の上にある灌木の根元に縄をくくりつけて、起こす。 山側の根の部分を踏み固める。根が浮き上がっていることがあるため。(客土も場合によっては必要) 垂直に起こさず、山側に起こすと、翌年の雪の重みで被害が大きくなる。 縄は、秋までに外すこと。 樹高が、最大積雪深の2.5倍になれば、一般的に不要となる。 最大積雪深が2m以上の場所は、植林は避ける。 |
|||||||||||||