
⑩木材を使おう
| 木材の性質 | 乾燥技術 | 木材加工 | 生活の中の木 | 日本家屋と寺社仏閣 | 林産物の規格 | 木材取引 | 新素材 | ||
| 木材乾燥の変遷 | 燃料革命 | 昔の大型木造建築 | |||||||
| 木炭 | 今の大型木造建築 |
| 木材乾燥の変遷:年代による変遷 |
| ①昭和48年(1973年)まで=オイルショック前まで 木材工業の発展とは、接着製品の発展でした。そこには、木材の寸法精度、狂い、割れ、塗装、二次加工と、木材の乾燥技術の発展と大きく関わっています。 木材を使う建築分野(プレハブ住宅)では、接着に関わる部分に色々な課題がありました。プレハブ住宅とは、家を建てる際、可能な限り工場で生産、加工、組立を行う方式の住宅のことです。このプレハブとは、「プレファブリケーション(Pre-fabrication)」のことで、現場で組み上げる前にあらかじめ部材の加工・組立をしておくことを意味しています。昭和初期にドイツの乾式組立構造として、プレハブ住宅の概念を輸入していましたが、住宅の大量需要というのがなく、工場製品化するには市場規模が小さかったため、一部の建築家による鉄骨系プレハブ建築が、走りと言われています。 その後、昭和34年(1959年)に、ベビーブームによる子供部屋不足の解決策として登場した離れの勉強部屋が、大和ハウス工業の「ミゼットハウス」がプレハブ住宅のイメージを形作ったと言われています。工場で製品が作られているため、組み立て時間が3時間と、半日で部屋が出来るというのが、画期的なことでした。ミゼット(midget)とは、小型という意味です。 そこから、様々なプレハブ住宅が登場してきます。軽量鉄骨(厚さ4mm以下の鋼材でつくられた鉄骨)にアルミサンドイッチパネル(プラスチック板とアルミシートで構成された化粧板)を取り付ける工法で作られた工業化住宅の第1号が、セキスイハウスA型です。居室に水廻りを備えっているのが特徴でした。 当時の一般住宅は、自然乾燥しかなく、新築住宅は、生材でも問題なかったのです。今は、3ヶ月で家を建てますが、当時は1年くらい時間をかけていたので、狂いや捻れが生ずれば、大工が鉋でケアしていました。今と違って、大工は木材と会話することが出来て当たり前の時代だったのです。逆に、新しい木材の香りが、喜ばれていた時代であった。このため、生材が乾燥する度に発生するパチパチという音を楽しんでいた。おおらかな時代でした。一方、伝統的な住宅の場合は、きちんと自然乾燥させ、狂いを取った木材を利用していました。貧乏人じゃないですので、待つことが出来たのです。 高度経済成長期の質より、量の時代でした。部材を除いて、建築用材においては、木材乾燥に余り重きを置いていなかった。 この当時にCLT材が登場しなかったのは、乾燥技術がなかったからです。 |
| ②昭和47年(1972年) 枠組壁工法(2×4工法)の登場から阪神・淡路大震災まで JASによって規定寸法が登場します。乾燥材、未乾燥材それぞれに仕様書があり、それに従って大工が家を作る時代になります。建築と農林規格が一緒になった。また、日本の在来工法の中に、プレカットが参入します。この過程で、枠組壁工法におけるプラットフォーム工法で、寸法変化、収縮の問題が発生します。未乾燥材の場合、現場で縮みが発生します。一方で乾燥材の場合は、縮みが余り発生しません。現場での混乱が発生します。結果、つなぎ止めている金物が、ズレることが起きます。金物に亀裂が入ることになります。 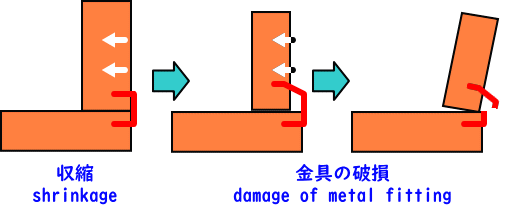 この結果、2x4工法では、生材(未乾燥材)が使われなくなります。乾燥材を使うに当たり、自然乾燥では時間が係ります。結果、人工乾燥が主流となります。住宅需要を満たすには、手っ取り早く乾燥した木材を市場に流す必要となったからです。 1%の収縮率だと、1mの板では、1cm、2%だと2cm短くなると言うことです。 同様に、軸組工法でも人工材が使われるようになります。パチパチ割れる音は、欠陥品じゃないかと言われるようになります。生材の香りは、寝かせていないねと言われるようになります。価値観の違いが、生まれてきて、これまで良かったことがダメ扱いになり、乾燥材を使わざるを得ない結果になります。 クレーム対応を避けるために、住宅を建てる側が集成材を受け入れるようになります。強度ではなく、客からのクレーム回避だったのです。 在来工法では、時間が係りますが、生材で家を建てつつ、乾燥して狂いを取っていく方法、乾燥材で建てる方法、集成材で建てる方法等、多様な方法が取られるようになります。 通常であれば、背割りを入れる柱だったけれども、割れが拡大するのは、見た目良くないと言うことになります。もう一つは、石膏ボードを割る事になります。 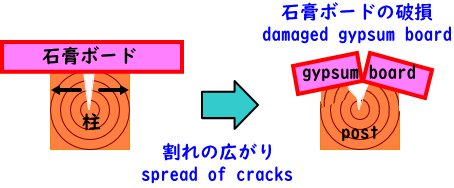 この時代になると、生材だと、伐採してから 1~2年で収縮が進み、木材に割れ、ねじれ、反りが発生します。パチパチという音が証拠です。その結果、床鳴り、壁紙の亀裂やシワ、接合部の緩み、隙間の発生等、住宅が歪むのです。そんな変形する木材で家を誰も建てる気がしません。隙間があった方が換気に良い時代は過ぎます。囲炉裏など、一酸化酸素中毒のリスクがあった時代は、隙間はリスク回避でした。しかし、エアコンが普及すれば、隙間は金の逃げ道になります。このため、寸法安定が重要となり、木材は含水率10~15%まで乾燥させる必要が生まれるのです。生もの扱いから、部品扱いになるのです。 このため、表面割れを起こしにくい方法を研究します。しかし、まだ、JAS製材は登場しません。燃え代設計が出来なかったからです。 昭和62年(1987年)には、大断面木造が登場し、燃えしろ設計、準耐火等も規格が登場します。集成材は計算できるが、木材では構造計算できないということになります。 |
| ③平成7年(1995年)の阪神・淡路大震災からの反省から 一般に、阪神・淡路大震災では、古い家、瓦屋根の家が倒壊したことで知られていますが、実態は、土台がしっかりしていなかった家が倒壊したのです。テレビ映像を通じて古い家と瓦屋根の家が目に映っていたのですが、土台との接合金物に原因があったのです。 この結果、家は●●構法ではなく、建築物の耐震性、①構造計画、②材料選択、③施工管理、④維持管理の4条件が重要となります。これらの反省を 平成12年(2000年)からの建築基準法性能規定化が節目になります。平成22年(2010年)からの木材利用促進法の登場で、これまで使われていなかった公共構造建築を含む、非住宅市場への木材の利用広がっていきます。まずは、公共施設からですが、中規模木造、耐火、仕様規定から材料の品質の安定化へと木材の立ち位置が変わってきた。 ・国産材→供給体制+乾燥 ・CLT、LVL、トラス構造→製材拡大+乾燥 ・高耐力→木質材料+金物+乾燥 ・混構造→寸法+乾燥 誤解を招く言い方になるが、少子化社会による住宅需要の縮小に対し、人工林からの木材のダブつきを解消するには、非住宅分野で消費して貰う必要が生まれ、その為には、安心して使えるように、狂いのない製材=乾燥した製材が必要な社会となった。国産材を使うことで、地域の活性化としての林業の回帰が生まれたとも言えます。 |
| セット法 |
2X4工法の種類
| バルーン工法 | プラットフォーム工法 |
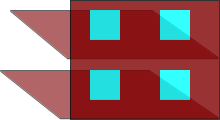 1階と2階は1枚の板 |
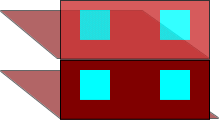 1階と2階は別々の板 |