
⑩木材を使おう
| 木材の性質 | 乾燥技術 | 木材加工 | 生活の中の木 | 日本家屋と寺社仏閣 | 林産物の規格 | 木材取引 | 新素材 | ||
| 木材乾燥の変遷 | 燃料革命 | 昔の大型木造建築 | |||||||
| 木炭 | 今の大型木造建築 |
| 燃料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和61年(1986年)から、土壌改良資材としての利用が始まる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料革命 ・プロパンガスの登場 日本におけるプロパンガスの歴史は昭和4年(1929年)の「グラーフ・ツェッペリン伯号」の来日。 この飛行船の燃料が、プロパンガスの始まり。その後、日米の対立から石油不足となり、LPガスで走るタクシーが登場。政府主導のLPガスでは知る大部分の車がタクシーだった名残で、今なおタクシーはLPGとのこと。 昭和28年(1953年)から家庭用LPガスが普及開始。ただし、石油の精製時に出来る副産物と言うことで、安定的な生産は行われていなかったのです。貯蔵タンクも未整備で、夏場は供給過剰、冬場はガス不足という環境だったのです。 薪炭に比べると、手軽に使えてカロリーが高いため、需要が高まっていきます。逆に言えば、だんだん薪炭の価値が落ちていくのです。素早く出来る料理か、美味しい料理を取るか、家庭はガスを、料理屋は炭を選択するのです。 昭和36年(1961年)に、LPガスの輸入が、ゼネラル瓦斯(JXTGエネルギー)の豪鷲丸により、開始されます。 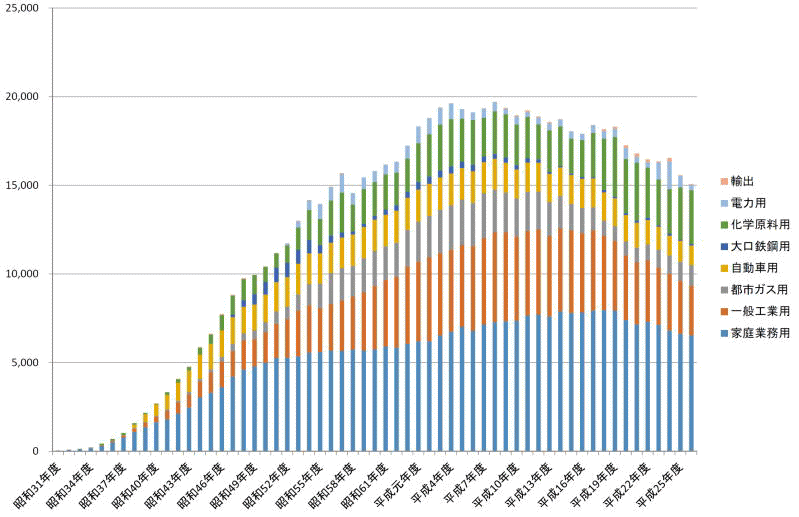 都市ガスは、(明治18年(1885年)に、渋沢栄一による東京瓦斯会社が誕生。明治35年(1902年)に、ガスかまどが登場し、
都道府県別 都市ガス普及率 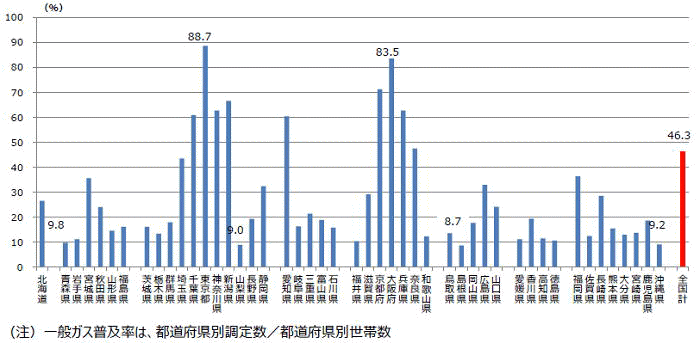 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||