
歴史
日本人が木を植えた歴史は、古く分かってるだけでも、紀元前4500年の山内丸山遺跡(青森県)、鳥浜遺跡(福井県)に、栗の木を植えたことが分かっています。

歴史
日本人が木を植えた歴史は、古く分かってるだけでも、紀元前4500年の山内丸山遺跡(青森県)、鳥浜遺跡(福井県)に、栗の木を植えたことが分かっています。
| 年号 | 造林の歴史 | 育種関係の歴史 |
| 紀元前4500年頃 | 栗林が出来る。 鳥浜遺跡、山内丸山遺跡 |
|
| 紀元前3000年頃 | 栗の精英樹選抜が行われる。 南方前池遺跡(岡山県) |
|
| 紀元前1000年頃 | 焼畑移動耕作が行われる。 四筒遺跡(福井県) |
|
| 紀元前100年頃 | 果樹栽培(梅、桃、杏)が行われる。 岡山遺跡(山口県) |
|
| 100年頃 | 木材需要の高まりか、乱伐が行われ、洪水が多発する。 | |
| 300年頃 | 瀬戸内海沿岸で製塩が盛んになり、薪の需要が増える。 | |
| 敏達12年 (583年) |
蘇我馬子亭跡より、庭園技術があった事が証明。 | |
| 推古15年 (607年) |
法隆寺が建造される。 | |
| 天武5年 (676年) |
森林伐採禁止令が出る。 飛鳥川上流の草本採取禁止、畿内山野の伐採禁止。 |
|
| 和銅元年 (708年) |
百姓の住宅地周辺に造林を許す。 (20~30歩)=(66~99m2) |
|
| 養老6年 (722年) |
焼畑が広がる | |
| 天平6年 (734年) |
出雲国集会帳の中の「桑漆帳」に、土地の立地区分によって植栽本数が規定されており、桑は、100~300根、漆は、40~100根する事と、定められていた。これらは、納税用。 | |
| 天平勝宝元年 (749年) |
東大寺の建設開始 | |
| 宝治3年 (759年) |
諸国の駅路(官道)に果樹を植えさせる。東大寺の普照法師による提言「應畿内七道諸國驛路兩遍種菓樹事」のこと。 畿道七道に果樹の並木を植え、旅人の安全と、快適な交通を確保する事を目的。 ※畿(大和・山城・摂津・河内・和泉)七道(東海道・東山道・北陸道・山陰道・山陽道・南海道・西海道) |
|
| 弘仁6年 (815年) |
機内、近江、丹後、播磨の国に、茶を植栽させる。 | |
| 弘仁12年 (821年) |
大和の国司、大和一円に潅田水辺の山林が持つ水源涵養、土砂崩壊防止機能を発揮させる観点から、水源林を禁伐にする。 | |
| 貞観8年 (866年) |
常陸国の鹿島神宮造営の材料として、4万本の杉の木、5700本の栗の木を神宮近くの空いている空間に植林し、造宮備林とする。 | |
| 天暦9年 (955年) |
阿波国里浦海岸に風潮除を兼ねて魚付き林の機能を持たせたクロマツ林を造成 | |
| 文治元年 (1185年) |
鎌倉幕府の政権樹立 街道整備として並木の植栽と保護育成が実施される。鎌倉時代~室町時代 |
|
| 建久元年 (1190年) |
熊野のスギが土佐藩幡多郡の熊野神社に移植される。 | |
| 仁治元年 (1240年) |
北条泰時が三河国の路表としてヤナギを植える。 | |
| 弘長元年 (1261年) |
大和の杉が能登国珠洲郡の春日神社に移植される。 | |
| 正和3年 (1314年) |
仙台領内で紀州藩熊野産の杉の種子による苗木作りが行われる。 | |
| 貞和5年 (1394年) |
熊野の杉は陸奥国江刺郡の正法寺へ移植させる。 | |
| 応仁元年 (1394年) |
京都北山において、初めて杉の台木による北山丸太栽培が始まる。 | |
| 康正2年 (1456年) |
上杉憲房(深谷上杉氏)が、深谷城周辺で行人の往来と戦時の防御といて、スギ、マツ、ケヤキを並木として植栽 | |
| 文明元年 (1469年) |
犬居町秋葉神社の社有林にスギ、ヒノキの植栽が始まる。天竜林業の開始 | |
| 文亀元年 (1501年) |
奈良県吉野川上郡で杉の植林が始まる。 吉野林業の開始 |
|
| 天文11年 (1542年) |
武田信玄が、甲斐国の釜無川の左岸に霞堤を作り、植林する。 | |
| 天文19年 (1550年) |
この頃から各地で山林の劣化、洪水防止のため、焼畑の禁止が行われる。 | |
| 元亀元年 (1570年) |
仙台藩は、海岸一体に砂防林を創設 | |
| 天正元年 (1573年) |
武蔵国高麗郡で、苗木数万本を上、かつ数町歩の原野を新開して植林する。 | |
| 天正2年 (1574年) |
織田信長が、東海道、東山道(中山道)の両脇に、マツ、ヤナギを街路樹として植栽 | |
| 天正13年 (1585年) |
上杉謙信は、領内の道路脇にマツ、カシワ、エノキ、ウルシを並木として植林 | |
| 文禄元年 (1592年) |
豊臣秀吉が九州に行く途中、里程標にクロマツを植栽 | |
| 慶長年間 (1596~ 1615年) |
前田利家、加藤清正が領内の街道にマツ・スギを植栽 | |
| 慶長5年 (1600年) |
尾張藩主徳川頼宣が尾張地方で人工林を始める。 | |
| 慶長8年 (1603年) |
江戸幕府の政権樹立 諸国の街道を拡幅し、道の両側にスギ、マツを主体に積極的に植栽。 |
|
| 元和4年 (1618年) |
長岡藩主牧野田忠晴、水野尾林(御水林)を設定する。水源涵養保安林制度の始まり | |
| 寛永年間 | 天領(長野県南佐久郡川上村)でのカラマツの植林が始まる。数百町歩植林 | |
| 寛永3年 (1626年) |
萩藩、20年毎に伐採する輪伐法を取り入れた「番組山」制度を導入。 | |
| 寛永8年 (1631年) |
青梅と西川の近辺で入会紛争勃発 | |
| 寛永19年 (1642年) |
幕府が天領等の代官に「木苗等を植えるべき場所に木苗を申すべきこと」と造林命令を出す。 | |
| 寛永20年 (1643年) |
幕府、御林奉行は代官所を通じて御林の地元村民に植林を命じて、耕地山野への植樹を申しつける。 日本版退耕還林 |
|
| 寛文元年 (1661年) |
幕府と諸藩は林産資源保続のため、下草の収集だけでなく、枯れ枝等の採集も禁止した御林を設ける。 この頃、資源不足から民間林業が出現し始める。 |
|
| 寛文10年 (1670年) |
玉川上水拡張工事において、両側の土手にマツ・スギを植栽。玉川上水羽村から代々木千駄木まで。 元文2年(1737年)川崎平ら右衛門定孝が、小金井桜とヨベレル玉川上水の堤にサクラを植栽 明和8年(1771年)には、エノキ、ナラ、クヌギなど11,838本の植栽。 |
|
| 元禄10年 (1697年) |
仙台藩、陸前国気仙郡の百姓半兵衞に熊野杉の実を渡し、私費で65万坪に杉を植林させる。 | |
| 元禄15年 (1702年) |
津軽藩主津軽伸政、外浜の明山へ杉4万本を植え付ける。 蜂須賀藩、造林とともに天然林の撫育と植栽、直播きを命ずる。 |
|
| 宝永5年 (1708年) |
木曽谷の大桑村でヒノキの植林開始。 | |
| 享保元年 (1716年) |
日田地方にスギの山挿しが始まる。 | |
| 享保2年 (1717年) |
墨田堤に徳川吉宗がサクラを植林 (4代将軍徳川家綱が常州桜川(今の茨城県桜川市岩瀬地区)のサクラを植えていたらしい) |
|
| 明和元年 (1764年) |
挿しスギ、挿しヒノキ造林についての具体的な方法が幕府より通達される | |
| 天明2年 (1782年) |
武蔵国秩父郡の吉田栗右衛門がスギ苗を2300本、8畝分の雑木林を伐開して植栽する。 播磨国多可郡の山口治右衛門が、雑木林を伐開して、スギとヒノキ6000本を植栽する。 |
|
| 享和2年 (1802年) |
諏訪郡原村でカラマツの造林を始める。 | |
| 文政7年 (1824年) |
日向国飫肥藩、杉の苗102万5000本を植林する。 | |
| 文政9年 (1826年) |
鳥取藩は、「諸木増殖仕法」を制定する。苗木を支給し、地主と植林者の分収形態を認める。 保安林を集落総出で行わせる。 |
|
| 天保年間 (1830~43年) |
高遠藩古見村の名主、塩原九郎右ェ門・伊豫之丞親子によるカラマツの播種、床替等の育苗技術の完成。 | |
| 天保8年 (1836年) |
伊勢国飯南郡波瀬村の田中彦左衛門が、飢饉に窮していた為に代償を問わず食料を買い与えた。民はその美徳に感じて30町歩の造林をした。(天保飢饉林) | |
| 弘化元年 (1844年) |
松代藩八幡御林でヒノキの植林が始まる。 | |
| 嘉永年間 (1848年) |
カラマツの育苗による植林が始まる。高遠藩古見村(現東筑摩郡朝日村)の名主が、秣刈り取り跡地の開墾のための耕作防風林を作るため、山引き苗を導入したが、生育不良から育苗からの造林を始める。 | |
| 嘉永5年 (1852年) |
小諸藩でカラマツの人工林造成(現存する最古の人工林) | |
| 嘉永7年・安政元年 (1854年) |
松代藩山田御林でヒノキの植林が始まる。 | |
| 安政4年 (1858年) |
小諸藩(長野県)で、諸木植え込み奨励として、カラマツ(山引き苗)での植林が行われる。 | |
| 明治元年 (1868年) |
「旧幕府領地ヲ直隷ト為スル令」が布告される。 徳川支配の旧幕府領地・森林原野は全て朝廷の御料となる。官地官林設定の始まり |
|
| 明治2年 (1869年) |
プロシア人のガルトネルが、函館にブナを植林。 七重村にガルトネル・ブナ林が現存 |
|
| 明治6年 (1873年) |
長野県でカラマツの育苗に取り組み始める。 北海道で長野県からカラマツの種を取り寄せ、播種を開始(失敗の連続) |
津田仙によって日本にニセアカシアが持ち込まれる。 |
| 明治7年 (8974年) |
銀座通りにクロマツとサクラを植栽 | |
| 明治8年 (1875年) |
街路樹として、内堀通りにニセアカシアを東京で初めて外来樹種として植栽。 | |
| 明治11年 (1878年) |
長野県で継続的なカラマツ造林が開始 | 山林局武田昌次をジャワに派遣し、小笠原試植用のキナ、コーヒー苗等を購入 |
| 明治12年 (1879年) |
オランダ人土木技師デレーケが報告書の中で、「治水は治山」と述べる。 長野県でカラマツの育苗に成功。 小諸市、大澤村(現佐久市)でカラマツの造林が始める。 |
米国三葉松、ドイツトウヒを西ヶ原試験場(渋谷区)に輸入(林試) |
| 明治13年 (1880年) |
銀座の外来樹が、クロマツとサクラからヤナギに植え替えられる。 北海道でカラマツの育苗に成功。炭鉱会社での造林(杭丸太用)が盛んになる。 |
山口県出張所で豪州産ユーカリ15種、ロシア産ニセアカシア1種の種子を導入(林試) |
| 明治16年 (1882年) |
西ヶ原試験場で培養したキナの苗150本鹿児島、沖縄両県下に植栽。(林試) | |
| 明治17年 (1883年) |
神奈川県官林にフランス海岸松を植栽(山林局) | |
| 明治22年 (1889年) |
フランス海岸松の種子3升を新潟大林区署の苗圃に播種。(山林局) | |
| 明治18年 (1894年) |
長野県からカラマツの種3升分を北海道に持ち込む。北海道でのカラマツの苗作り本格化。 | |
| 明治19年 (1895年) |
ノースロップ博士が来日。アーバーデイ(愛林日)の精神を説く 明治政府が学校林の設置の訓令を出す。11月3日の明治天皇誕生日を学校植栽日とする。 |
フランスからフランス海岸松の種子を取寄せて播種、石川県安宅国有林に植栽 |
| 明治30年 (1897年) |
最初の森林に関する一般法として、森林法が公布される。 | 府県による直営苗圃・苗木下付の開始 |
| 明治31年 (1898年) |
本多静六博士の提唱で4月3日の神武天皇祭が植栽日になる。 | |
| 明治32年 (1899年) |
国有林野特別経営事業が始まる。 (不要国有林野を払い下げた代金を積み立てて国有林野を造林等で改良整備する事業) |
|
| 明治33年 (1900年) |
西日本の脊悪地にヒノキの造林が盛んになる。 | 林業試験場(目黒区)にハンテンボクを播種、インド産モリンダトウヒ、ドイツ産エキセルサトウヒを植栽。 |
| 明治37年 (1904年) |
ドイツトウヒ、ヨーロッパアカマツ等が群馬県の前橋営林局小根山林業試験地に植林 | |
| 明治40年 (1907年) |
木材工芸品の原材料となる広葉樹植栽のための苗木配布を開始 東京市が街路需要の苗木育成に着手(いちょう、スズカケノキなど10種) |
|
| 明治41年 (1908年) |
宮城県、岐阜県で、最初の県行造林を実施。 (県が土地所有者と分収契約を結び、民有林野(市町村有林野も含む)に対して造林を行い、その収益を土地所有者と分収する) |
山林局は小笠原及び台湾にコルクガシを移植奨励し、小笠原にゴム栽培を奨励。 |
| 明治42年 (1909年) |
ストローブマツ、ドイツトウヒを小根山林業試験地に植栽 | |
| 明治43年 (1910年) |
荒廃していた地域住民に共用されていた林野(薪・草)において植栽などの補助 東京市は、街路樹を下谷の御徒町通りをスタートとして、3,000本/年の植栽をはじめる。大正8年頃に25,000本となるが、関東大震災による10,000本程度となる。 秋田県小坂鉱山周辺の煙害地にニセアカシアの植栽開始。 |
|
| 大正元年 (1912年) |
奥羽本線磐越線に雪崩防止林が初めて造成される。 |
|
| 大正3年 (1914年) |
山林局林業試験場種子鑑定規則 | |
| 大正8年 (1919年) |
樹苗養成奨励規則 (大正8年~昭和24年) (昭和27年~昭和31年) |
|
| 大正9年 (1920年) |
明治神宮竣工(全国から献本数95,559本+27,013本、計12万2,572本が植栽) 公有林野官行造林が始まる |
|
| 昭和2年 (1927年) |
水源涵養機能の回復のため、無立木地における植栽に補助を開始。 東京市は樹木の防災機能に着目し、帝都復興事業としてイチョウの木を中心に街路樹を植栽開始する。17年後の昭和18年には、10万本を超える。しかし、終戦までに65%が消失。なお、10%は、盗伐で占められ、3万本程度に落ち込む |
|
| 昭和4年 (1929年) |
造林奨励規則が公布される。(初めて私有林まで補助対象と拡大した) | |
| 昭和8年 (1933年) |
4月2~4日までの3日間をアンリ日とし、全国一斉に愛林行事をすることを提案(提案者は、大日本山林会会長和田国次郎、農林次官石黒忠篤、山林局長村上竜太郎) | |
| 昭和9年 (1934年) |
第1回愛林日に、日本最初の中央植樹行事が茨城県の鬼が作国有林(桜川市真壁町大字羽鳥の筑波山)で実施。 | 造林用種子払下規則 (同規則に依り払下ぐべき種子の種類、価格及配給区域) |
| 昭和14年 (1939年) |
林業種苗法 制定 | |
| 昭和15年 (1940年) |
林業用種子採取奨励事業 (昭和15年~24年)、(昭和27年~30年)(昭和32年~) |
|
| 昭和18年 (1943年) |
需給調整地区別協議会 | |
| 昭和20年 (1945年) |
東京大空襲で中央植樹祭は中止 | |
| 昭和22年 (1947年) |
森林愛護連盟が林業六団体によって結成される。会長は、徳川宗敬。 4月4日に平成天皇(当時皇太子殿下)を迎えて、愛林日植栽行事が復活する。 |
国有林野で民需用苗木養成事業 (昭和22年~27年) |
| 昭和23年 (1948年) |
東京都青梅市天神平に天皇皇后両陛下を迎えて記念植樹行事を行う。GHQ天然資源局林業局の幹部も家族同伴で参加 緑の週間(4月1~7日)が設けられる。 |
|
| 昭和24年 (1949年) |
神奈川県箱根仙石原で記念植樹行事 |
|
| 昭和25年 (1950年) |
国土緑化推進委員会が結成される。 愛林日の中央記念植樹行事が、「植樹行事及び国土緑化大会」となる。 第1回植樹行事及び国土緑化大会(山梨県:荒廃地造林) 「緑の羽募金」が始まる。 (赤い羽根募金は昭和22年から) 「全日本学校植樹コンクール」の実施を開始する。 国土緑化運動ポスター原画と標語の募集を開始する。 |
|
| 昭和26年 (1951年) |
第2回植樹行事及び国土緑化大会(群馬県:火山灰地帯造林) |
林業種苗法第10条の規定に基きすぎ等の種苗の配付区域指定 |
| 昭和27年 (1952年) |
第3回植樹行事及び国土緑化大会(静岡県:入会原野造林) | |
| 昭和28年 (1953年) |
第4回植樹行事及び国土緑化大会(千葉県:海岸砂地造林) | |
| 昭和29年 (1954年) |
第5回植樹行事及び国土緑化大会(兵庫県:脊悪林地造林) | |
| 昭和30年 (1955年) |
第6回植樹行事及び国土緑化大会(宮城県:林種転換拡大造林) | |
| 昭和31年 (1956年) |
第7回植樹行事及び国土緑化大会(山口県:荒廃公有林造林) | 林木育種事業指針 |
| 昭和32年 (1957年) |
根釧原野の一角で、カラマツ林を作るパイロットフォレストが開始される。 第8回植樹行事及び国土緑化大会(岐阜県:公有林復興、学校林、青年団林造林) |
林木育種事業の推進について 林木育種事業の実施等について |
| 昭和33年 (1958年) |
分収造林特別措置法公布 第9回植樹行事及び国土緑化大会(大分県:原野造林) |
山林用主要苗木の標準規格設定について |
| 昭和34年 (1959年) |
第10回植樹行事及び国土緑化大会(埼玉県:林種転換) | |
| 昭和35年 (1960年) |
「グリーンスカウト運動」を提唱。青少年による緑化運動組織(日の緑の少年団)が誕生する。 第11回植樹行事及び国土緑化大会(山形県:積雪寒冷地帯、林種転換拡大造林) |
|
| 昭和36年 (1961年) |
森林開発公団が造林を開始 (官行造林も継承) 第12回植樹行事及び国土緑化大会(北海道:積雪寒冷地帯の拡大造林と屋敷林の造成) |
林業用優良種苗生産需給調整要綱 苗木生産指導事業・苗木生産管理事業 (昭和36年~44年) |
| 昭和37年 (1962年) |
第13回植樹行事及び国土緑化大会(福井県:湿雪地帯の拡大造林と森林生産力の増大) | カラマツ苗木を対象とする先枯病防除の緊急措置について |
| 昭和38年 (1963年) |
第14回植樹行事及び国土緑化大会(青森県:粗放林野の拡大造林と生産力増強に基づく住民の所得向上) | |
| 昭和39年 (1964年) |
林業基本法が公布される。 第15回植樹行事及び国土緑化大会(長野県:入会原野の造林推進) |
|
| 昭和40年 (1965年) |
第16回植樹行事及び国土緑化大会(鳥取県:林種転換による拡大造林) | 1次林構事業 (昭和40年~49年) |
| 昭和41年 (1966年) |
「県の木」が制定される。 第17回植樹行事及び国土緑化大会(愛媛県:精英樹による拡大造林) |
|
| 昭和42年 (1967年) |
国土緑化推進員会が、社団法人化される。 第18回植樹行事及び国土緑化大会(岡山県:拡大造林と環境緑化) |
優良種苗確保事業実施要領について 苗木生産協業化促進事業 (昭和42年~46年) |
| 昭和43年 (1968年) |
第19回植樹行事及び国土緑化大会(秋田県:入会林野の整備と拡大造林の推進) | |
| 昭和44年 (1969年) |
第20回植樹行事及び国土緑化大会(富山県:低質広葉樹の高度利用と拡大造林) | |
| 昭和45年 (1970年) |
植樹行事及び国土緑化大会から「植樹行事及び国土緑化大会」に名称が変更される。 第21回全国植樹祭(福島県:「後継者の森」造成) |
林業種苗法全面改正 種苗表示証明制度運営補助 (昭和45年~) |
| 昭和46年 (1971年) |
第22回全国植樹祭(島根・広島県:多目的森林開発と環境緑化) | 農林水産大臣の指定する種苗の配布区域を定める件 種子精選施設設置事業(昭和46年~50年) |
| 昭和47年 (1972年) |
第23回全国植樹祭(新潟県:拡大造林と環境緑化) | 協業化促進施設事業 (昭和47年~51年) |
| 昭和48年 (1973年) |
下刈りなどに対する補助を開始。その後、除伐、間伐を補助対象に追加し、対象となる齢級も拡大 第24回全国植樹祭(宮崎県:自然の保護と創出) |
2次林構事業 (昭和48年~59年) |
| 昭和49年 (1974年) |
第25回全国植樹祭(岩手県:自然と産業が調和する豊かな緑の創造) | |
| 昭和50年 (1975年) |
第26回全国植樹祭(滋賀県:水と緑のふるさとづくり) | |
| 昭和51年 (1976年) |
第27回全国植樹祭(茨城県:緑を育て守ろう大地) | 苗木低温貯蔵庫設置 (昭和51年~53年) |
| 昭和52年 (1977年) |
皇太子同妃殿下を迎えて第1回「全国育樹祭」(大分県)が始まる。 第28回全国植樹祭(和歌山県:みんなで育てるみどりの郷土) 第1回全国育樹祭(大分県別府市:豊かな緑のふるさとづくり) |
種苗生産団地育成事業 (昭和52年~56年) |
| 昭和52年 (1977年) |
第29回全国植樹祭(高知県:防災も緑できずくふるさとづくり) 第2回全国育樹祭(秋田県田沢湖町:育樹できずこうみどりの郷土) |
|
| 昭和53年 (1978年) |
第30回全国植樹祭(愛知県:緑で結ぼう山村(やま)と都市(まち)) 第3回全国育樹祭(福岡県宇美町:育てよう緑と木の豊かな郷土) |
|
| 昭和54年 (1979年) |
第31回全国植樹祭(三重県:緑と太陽豊かなくらし) 第4回全国育樹祭(福井県丸岡町:緑できずこう豊かな未来) |
苗木需給安定基金造成事業 (昭和54年~62年) 種子貯蔵庫設置事業 (昭和54年~57年) |
| 昭和55年 (1980年) |
第32回全国植樹祭() 第5回全国育樹祭(新潟県黒川村:育てよう緑と人と豊かな心) |
林木育種事業運営要綱 |
| 昭和56年 (1981年) |
||
| 昭和57年 (1982年) |
||
| 昭和58年 (1983年) |
分収育林制度、森林整備法人の法制化が始まる。 |
|
| 昭和59年 (1984年) |
21世紀森林作り委員会が設置される。 |
|
| 昭和60年 (1985年) |
||
| 昭和61年 (1986年) |
21世紀森林作り委員会が「国民参加の森林作り」を提言する。 水源税(森林・河川緊急整備税)創設の運動が起きるが、利水者側から反対でポシャる。 |
|
| 昭和62年 (1987年) |
||
| 昭和63年 (1988年) |
(社)国土緑化推進委員会が、(社)国土緑化推進機構に名称を変更する。 「緑と水の森林基金」が創設される |
|
| 平成元年 (1989年) |
4月29日が「みどりの日」に制定され、国民の休日となる。 緑の週間が4月23日からの1週間となる。 |
|
| 平成2年 (1990年) |
||
| 平成3年 (1991年) |
||
| 平成4年 (1992年) |
||
| 平成5年 (1993年) |
||
| 平成6年 (1994年) |
||
| 平成7年 (1995年) |
緑の羽募金が「緑の募金」に法制化(緑の募金による森林整備の推進に関する法律)される。この結果、国内の緑化から世界の緑化も可能となる。 | |
| 平成8年 (1996年) |
||
| 平成9年 (1997年) |
||
| 平成10年 (1998年) |
||
| 平成11年 (1999年) |
||
| 平成12年 (2000年) |
||
| 平成13年 (2001年) |
||
| 平成14年 (2002年) |
||
|
|
||
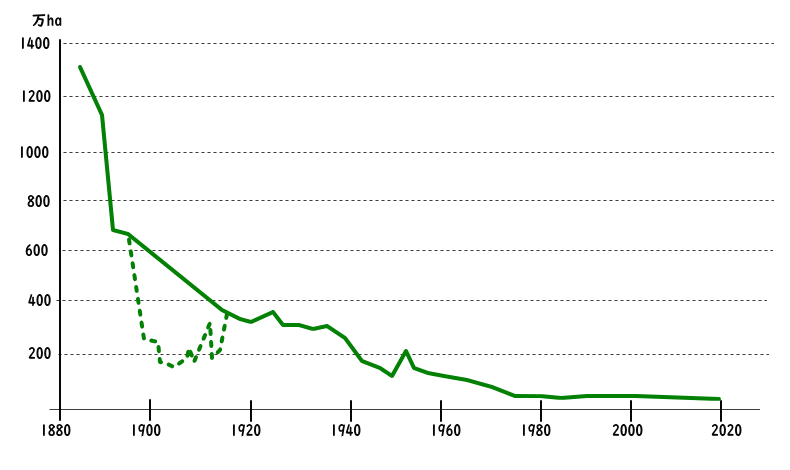 草地面積の推移 1890~1915年頃のデータの乖離より、勝手に修正 |
||