
⑦森林・林業関係を勉強・就職するためには?
1.高等学校
1-1.カリキュラム
1-2.取得できる公的資格
1-3.就職先
2.専門学校(大学校)
2-1.カリキュラム
2-2.取得できる公的資格
2-3.就職先
3.大学
3-1.カリキュラム
3-2.取得できる公的資格
3-3.就職先
4.資格の内容
5.学校リスト

⑦森林・林業関係を勉強・就職するためには?
1.高等学校
1-1.カリキュラム
1-2.取得できる公的資格
1-3.就職先
2.専門学校(大学校)
2-1.カリキュラム
2-2.取得できる公的資格
2-3.就職先
3.大学
3-1.カリキュラム
3-2.取得できる公的資格
3-3.就職先
4.資格の内容
5.学校リスト
日本では、小学校(6年間)と中学校(3年間)の計9年間が義務教育となっており、国民は必ず義務教育を受けなければならない。一般的には中学卒業後、高校(3年間)に進学し、その後、就職、専門学校、大学等に進路を進める。森林・林業分野における教育機関は、高等学校、専門学校(大学校)、大学の3種類に分類される。高等学校と専門学校(大学校)は、現場における即戦力の担い手を、大学は持続可能な社会を達成できるような研究や調査を通じて、課題解決の出来る人材を育成している。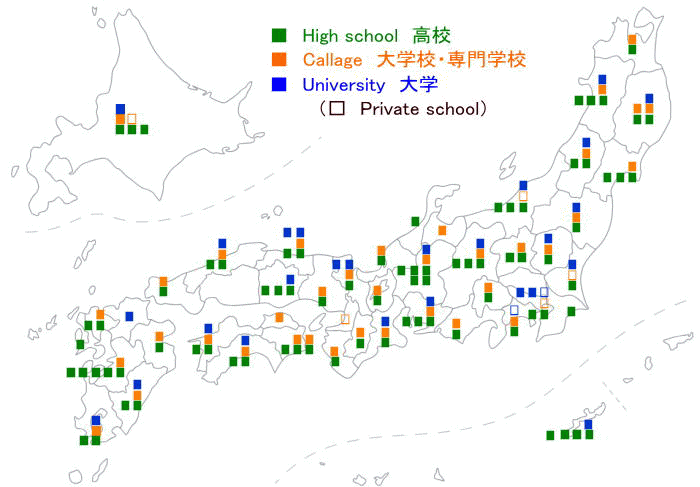 学校の配置図 1.高等学校 47都道府県中、41都道府県に、林業についての専門技術や知識を習得するために林業系の学科が併置されている79の高等学校があり、森林・林業分野の担い手を育成している。全ては、公立学校になっており、農業・畜産部門、食品加工部門、機械部門、電気部門など、他部門と一緒に運営されている。各校とも恵まれた自然環境を活用し、自然と人間生活の調和を体験的に学べる場となっている。学生は、森林経営、木材流通について理解するとともに、森林の多面的機能についても学び、森林の管理や整備を行う技術者、木材を加工する技術者、キノコ等林産物を生産する技術者になるための知識や技術を習得する。 1-1.カリキュラム 下記のプログラムが基本になっている。なお、学校によっては、園芸や都市緑化等、地域にニーズに合わせたリキュラムもある。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2.取得できる公的資格 一般的な高等学校とは異なり、卒業後、現場の実践となるため、様々な資格取得が出来るようになっている。これらの資格が無ければ、従事できない仕事が多い。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3.就職先 林業分野の公務員、森林組合、林業事業体(造林関係、製材関係、製紙関係、林産品関係等)の他、大学の森林分野に進学している。就職に当たっては、都道府県の地方振興局が事業体と高校生との間を取り持つ交流会を実施しており、就職を支援している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.専門学校(大学校) 26の専門学校があり、私立学校の5つを除いて公立ないしは行政の支援で運営された専門学校となっている。特に、多くの公立高校は地域の林業の後継者不足という課題を解決するために、現場での即戦力となる人材育成を目的として設立されている経緯がある。このため、公立の専門学校の方がより実践的学習内容となっている。期間は、1~2年となっており、実習により力を入れている。実習場所の多くは、都道府県の林業部門が持っている研修所や研究機関に間借りしていることが多い。公立の場合は、県民のみ受講できる学校と、全国から募集を行う等、その県の状況によって対応が異なっている。全国から募集する場合は、必要性があるが県内からの人員確保が難しい事、人が集まることで、地域経済の活性化、人材確保として地元への就職等の理由である。なお、授業料が無料の場合もある。無料の県の場合は、卒業後、その県内の森林組合、林業会社に就職することが前提となっている。 2-1.カリキュラム 高校と異なり、専門学校では資格を取得するための講義が設定されている。なお、一部には、下記の技能を高める研修の他、課題解決能力を高めるため、一般教養を取り入れているところも出始めている。 高校や大学と異なり、卒業後、現場での即戦力なるための内容となっている。このため、資格取得のための研修が多くなっている。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-2.取得できる公的資格 造林に特化しており、高校と異なり、木材加工等の林産関係の資格は無い。なお、林産関係は、都道府県や市町村が運営する職業能力開発施設が担っている。職業能力開発施設は就業支援であるため、学費は無料となっている。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3.就職先 林業分野の公務員、森林組合、林業事業体(造林関係、製材関係、製紙関係、林産品関係等)の他、大学の森林分野に進学している。就職に当たっては、都道府県の地方振興局が事業体と高校生との間を取り持つ交流会を実施しており、就職を支援している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.大学 全国に、29大学(国立24校、公立3校、私立2校)がある。通常は、4年制である。大学では、森林の様々な機能を保護・再生することで、地域の環境、森林資源および地球環境の保全を図り、持続的に生産、利用する技術や理論を学び、現場で役立つ調査・研修手法を習得する。これらを通じて、自然と調和した生産基盤作り、農山村の振興、生活環境の維持と創出に貢献出来る柔軟な判断力を養い、視野の広い人材を育成している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-1.カリキュラム 専門分野のみならず、一般教養にも力を入れている。主な内容は以下の通りである。なお、一部の専門学校(大学校)では、課題解決能力を高めるため、一般教養を取り入れているところも出始めている。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-2.取得できる公的資格 大学4年間で修得する内容によって、以下の資格が取得ないしは受験資格を得ることが出来る。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-3.就職先 大学院に進学するほか、森林・林業・林産業分野の国家公務員、地方公務員、林業事業体(造林関係、製材関係、製紙関係、林産品関係、住宅関係、化学工業等)、生態・環境系NPO等を含め幅広い分野に就職している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.資格の内容 日本では、危険性が伴う仕事に対し、有資格者のみが出来る仕組みとなっている。資格を取得するためには、講習会への参加、自己研鑽等が求められている。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県 | 高校名 | 大学校・専門学校 | 大学 |
| 北海道 | 旭川農業高校(森林科学科) 岩見沢農業高校(森林科学科) 帯広農業高校(森林科学科) |
道立北の森づくり専門学院 札幌工科専門学校 |
北海道大学農学部 森林科学科 |
| 青森県 | 五所川原農林高校 (森林科学科) | 青い森林業アカデミー | - |
| 岩手県 | 盛岡農業高校(環境科学科) 久慈東高校(総合学科(環境緑化系列 森林生態科目群)) |
いわて林業アカデミー 釜石・大槌バークレイズ林業スクール |
岩手大学農学部 森林科学科 |
| 宮城県 | 小牛田農林高校 柴田農林高校(森林環境科) 柴田農林高校川崎校 |
みやぎ森林・林業未来創造カレッジ | - |
| 秋田県 | 鷹巣農林高校(森林環境科・緑地環境科(森林環境コース)) 大曲農業高校(農業科学科(環境緑地系)) 秋田北鷹高校(緑地環境科(森林環境コース)) |
秋田県林業研究研修センター 秋田県林業トップランナー養成研修 (愛称:秋田林業大学校) |
秋田県立大学生物資源科学部 生物環境科学科 |
| 山形県 | 村山産業高校(農業環境科) 置賜農業高校(食料環境科) |
山形県立農林大学 | 山形大学農学部 食料生命環境学科 |
| 福島県 | 会津農林高校(森林環境科) | 林業アカデミーふくしま | 福島大学農学群食農学類 生産環境学コース |
| 茨城県 | 大子清流高校(農林科学科) | 鯉淵学園農業栄養専門学校 | 筑波大学生命環境学群 生物資源学類 |
| 栃木県 | 鹿沼南高校(環境緑地科(林業コース)) | 栃木県林業大学校 | 宇都宮大学農学部 森林科学科 |
| 群馬県 | 利根実業高校(グリーンライフ科(森林科学コース)) 勢多農林高校(グリーンライフ科(グリーンライフコース)) |
群馬県立農林大学校 | - |
| 埼玉県 | 秩父農工科学高校(森林科学科) | - | - |
| 千葉県 | 君津青葉高校(総合学科(環境系列)) | - | - |
| 東京都 | 青梅総合高校(総合学科(生命・環境系列)) 大島高校(農林科) |
東京環境工科専門学校 | 東京大学農学部 応用生命科学課程 森林生物科学専修 環境資源科学課程 森林環境資源科学専修 環境資源科学課程 木質構造科学専修 東京農工大学農学部 地域生態システム学科 環境資源科学科 東京農業大学地域環境科学部 森林総合科学科 |
| 神奈川県 | 吉田島高校(環境緑地科) | かながわ森林塾 | 日本大学生物資源科学部 森林資源科学科 |
| 新潟県 | 加茂農林高校(環境緑地科(緑地工学コース)) 高田農業高校(生物資源科(森林資源コース)) 村上桜ヶ丘高校(総合学科(農業森林系列)) |
日本自然環境専門学校 | 新潟大学農学部 生産環境科学科 |
| 富山県 | TOGA森の大学校 | - | |
| 石川県 | - | - | |
| 福井県 | 福井農林高校(環境工学科(環境緑化コース)) | ふくい林業カレッジ | - |
| 山梨県 | 農林高校(森林科学科) | 専門学校山梨県立農林大学校 | - |
| 長野県 | 上伊那農業高校(緑地創造科) 木曽青峰高校(森林環境科) 下高井農林高校(グリーンデザイン科) |
長野県林業大学校 | 信州大学農学部 農学生命科学科 |
| 岐阜県 | 岐阜農林高校(森林科学科) 郡上高校(森林科学科) 加茂農林高校(森林科学科) 恵那農業高校(環境科学科) 飛騨高山高校(環境科学科) |
岐阜県立森林文化アカデミー | 岐阜大学応用生物科学部 生産環境科学課程 |
| 静岡県 | 天竜高校(農業科(森林科)) | 静岡県立農林大学校 | 静岡大学農学部 生物資源科学科 |
| 愛知県 | 安城農林高校(森林環境科) 田口高校(林業科) 猿投農林高校(林産工芸科) |
あいち林業技術強化カレッジ | 名古屋大学農学部 生物環境科学科 |
| 三重県 | 久居農林高校(環境情報科(環境保全コース)) | みえ森林・林業アカデミー | 三重大学生物資源学部 資源循環学科 |
| 滋賀県 | 甲南高校(総合学科(生物と環境系列)) | 滋賀もりづくりアカデミー | - |
| 京都府 | 北桑田高校(森林リサーチ科) | 京都府立林業大学校 | 京都大学農学部 森林科学科 京都府立大学生命環境学部 森林科学科 |
| 大阪府 | 大阪動植物海洋専門学校 | - | |
| 兵庫県 | 山崎高校(森林環境科学科) | 兵庫県立森林大学校 | - |
| 奈良県 | 吉野高校(森林科学科) | 奈良県フォレスターアカデミー | - |
| 和歌山県 | 熊野高校(総合学科(グリーンマスター系列)) | 和歌山県農林大学校 | - |
| 鳥取県 | 智頭農林高校(森林科学科) 倉吉農業高校(環境科) |
にちなん中国山地林業アカデミー | 鳥取大学農学部 生命環境農学科 公立鳥取環境大学環境学部 環境学科 |
| 島根県 | 松江農林高校(総合学科(地域クリエイト系列)) 出雲農林高校(環境科学科) |
島根県立農林大学校 | 島根大学生物資源科学部 農林生産学科 |
| 岡山県 | 勝間田高校(総合学科(森林系列)) 新見高校(生物生産科) 高梁城南高校(環境科学科) |
- | 岡山大学農学部 総合農業科学科 |
| 広島県 | - | - | |
| 山口県 | 山口農業高校(環境科学科(森林資源コース)) | やまぐち森林・林業未来維新カレッジ | - |
| 徳島県 | 那賀高校(森林クリエイト科) 池田高校(三好校)(環境資源科) 城西高校(植物活用科) |
とくしま林業アカデミー 三好林業アカデミー |
- |
| 香川県 | 農業大学校 林業・造園緑化コース |
- | |
| 愛媛県 | 上浮穴高校(森林環境科) 伊予農業高校(特用林産科) |
南予森林アカデミー | 愛媛大学農学部 生物環境学科 |
| 高知県 | 高知農業高校(森林総合科) 幡多農業高校(グリーン環境科) |
高知県立林業大学校 | 高知大学農林海洋科学部 農林資源環境科学科 |
| 福岡県 | - | 九州大学農学部 生物資源環境学科 |
|
| 佐賀県 | 伊万里農林高校(森林工学科) 伊万里実業高校(森林環境科) |
さが林業アカデミー | - |
| 長崎県 | 諫早農業高校(環境創造科) | - | - |
| 熊本県 | 阿蘇中央高校(グリーン環境科) 矢部高校(林業科学科) 八代農業泉分校(グリーンライフ科) 芦北高校(林業科) 南稜高校(総合農業科) |
くまもと林業大学校 | - |
| 大分県 | 日田林工高校(林業科) | おおいた林業アカデミー | - |
| 宮崎県 | 日南振徳高校(地域農業科) 門川高校(総合学科) |
みやざき林業大学校 | 宮崎大学農学部 森林緑地環境科学科 |
| 鹿児島県 | 伊佐農林高校(農林技術科) 鹿屋農業高校(緑地工学科) |
かごしま林業大学校 | 鹿児島大学農学部 農林環境科学科 |
| 沖縄県 | 北部農林高校(林業緑地科) 中部農林高校 南部農林高校 八重山農林高校(グリーンライフ科) |
- | 琉球大学農学部 亜熱帯地域農学科 亜熱帯農林環境科学科 |
2020年4月時点
トップに戻る